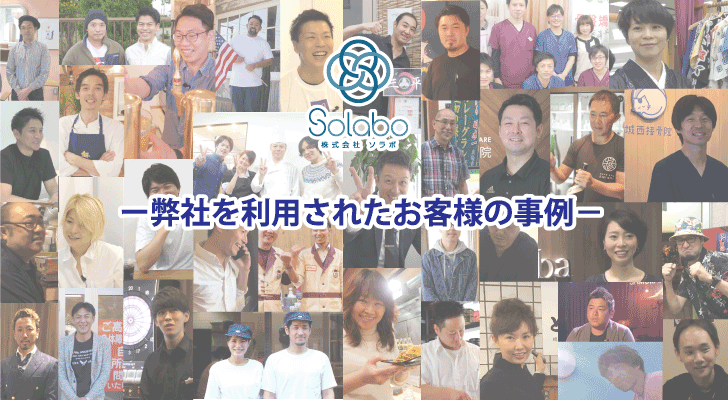事業者が避けて通れない「領収書」の発行。5万以上だと税法で収入印紙が必要だったり、金額によって印紙代が変わったりと、気を遣います。
紙を使わないペーパーレスでのビジネス展開が当たり前になりつつある今、どういう領収書が求められるのでしょうか。
この記事で、領収書の基本、そして、印紙代を節約できる領収書の電子発行について見ていきましょう。
1.領収書に印紙が必要な理由
領収書は、報酬が支払われたことを証明するために取引先に提出する、一枚ものの文書です。税法上では、金銭・有価証券の受理を証明するための受取書に当たります。普段、何かモノ・サービスを買ったときに、渡されるレシートと同じものです。
課税文書に当たる書類には、税法上、印紙税が課税されます。印紙税は、課税対象の文書を作成・発行する人が、該当する金額の収入印紙を貼り、税金を納める仕組みです。
領収書が課税対象になる一般的な条件は「税抜で領収した金額が5万円を超える場合」かつ「電子発行でない場合」(※)です。
(※ その他、震災や公益法人などでの特例の免除条件もあります。詳しくは、国税庁ウェブサイト 印紙税のページを参照ください)
税抜で領収した金額が5万を超え、紙で領収書を発行する場合、収入印紙を貼る必要があります。印紙は、郵便局やコンビニで購入できます。必要な印紙の種類は次を参考にしてください。
| 記載金額 | 税額 |
|---|---|
| 5万円未満のもの | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下のもの | 600円 |
| 300万円を超え 500万円以下のもの | 1000円 |
| 500万円を超え 1000万円以下のもの | 2000円 |
詳しくは「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」(国税庁ウェブサイト)をご確認ください。
なお、印紙が必要なのに貼っていないと、過怠税として印紙の額面の3倍にあたる金額を支払わなければならない場合がありますので、注意しましょう。詳しくは「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」(国税庁ウェブサイト)をあわせてご確認ください。
電子発行って?
「電子発行」と呼ばれる手段で領収書を発行すれば、収入印紙の添付は不要になります。
「電子発行」を具体的にいうと、領収書をウェブサイト上で発行する、領収書をメールでやりとりする、領収書をFAXでやりとりする、と言った「紙」のやりとりです。パソコンで作成しても、領収書を印刷して手渡し・郵送では、印紙代が必要になりますので、注意しましょう。
「電子発行」について詳しく知りたい方は「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」(国税庁ウェブサイト)をご確認ください。
2.印紙代節約!クラウド型サービスで領収書を電子発行しよう

領収書を発行するとき、書式に悩む人もいるでしょう。
インターネットで検索すると、自由にダウンロードして使える領収書テンプレートがあります。カラフルなデザイン性の高いものもあります。しかし、経費削減でカラー印刷を禁止する企業では、コピーをとる場面で読みにくくなる可能性も考えられます。
また、カラフルな資料はPDF形式であってもデータ容量が大きくなりがちで、端末に負荷がかかるケースがあります。領収書の書式は、白黒でもはっきり読めるような、シンプルなものを選ぶよう心がけましょう。
データはPDF形式で保存することがおすすめです。PDF形式は、他のデータ形式と違い、情報の改ざんがしにくいため、正式な書類データに採用されるファイル形式です。もしFAXを送る場合などで印刷が必要な場合でも、PDF形式は印刷時に文字や表示が崩れにくいファイル形式ですので、PDFファイルをそのまま印刷すれば画面で見た通りに印刷できるはずです。
文書ソフトウェアの領収書テンプレート
パソコンに入っている文書ソフトウェアのテンプレートで領収書を作る人もいます。シンプルなデザインで、必要な項目も網羅されているため、基本的にはそのままPDF形式のデータにして取引先に送っても問題ないでしょう。
ただし、領収書の文書を使いまわしたときに起こる、修正もれには注意しましょう。但し書きが間違っていたり、宛先を修正し忘れて別の取引先名で発行してしまったりといったミスも考えられます。取引先の信用を失う事態は避けましょう。
また、パソコンに領収書のデータを保管しておくと、パソコンが壊れた時に、それまでのデータを活かした領収書の作成ができなくなってしまいます。データのバックアップを取っていれば影響は小さくできます。
クラウド型サービスの領収書
クラウド型のサービスは文字を入力するだけで手軽に領収書を発行できます。
クラウドサービスとは「インターネットさえあれば、専用のソフトウェアをパソコンに入れなくてもすぐ使える」という、ウェブサイト側にデータを保管できるサービス全般を指す概念です。つまり、自前のパソコンがいきなり壊れても、別のパソコンからインターネットにつないでIDとパスワードを入力すれば、これまで通り、領収書を見たり作ったりできます。
必要な箇所だけを入力するため、領収書のファイルを使いまわして作るよりも間違いのない領収書を作ることができるでしょう。
RAKUDAクラウド請求サービス
無料で利用できるクラウドサービス「RAKUDAクラウド請求書サービス」を紹介します。
会員登録は必要ですが、これまでの領収書を一覧で確認できるだけでなく、見積書の入力内容を流用して請求書や納品書を作れたり、過去の請求書を流用して新しい請求書を作れたり、という機能があります。入金や受注のステータス管理もできるので、案件の進捗管理にも便利です。
次のURLはRAKUDAクラウド請求書サービスの使用体験のページです。興味のある人はみてみてください。
「請求書を見たことない・パソコン苦手なインターン生でも3分で請求書が作れる!?RAKUDAクラウド請求書サービスを使ってみた!」
3.保存することを忘れずに!

申告の条件にもよりますが、確定申告の期限日から数えて最短で5年、最長で7年、領収書は保存しなければなりません。
現在、電子帳簿保存法の改正により、全てのケースの領収書は、正しく電子保管することで紙の原本が廃棄できます。PDF形式で発行した領収書のデータ需要は今後も増えることでしょう。
まとめ
領収書は重要ですが、なるべく手をかけたくないものです。
領収書を電子発行することで印紙代を節約することができます。自分にあった方法で電子発行の領収書を作成してみましょう。