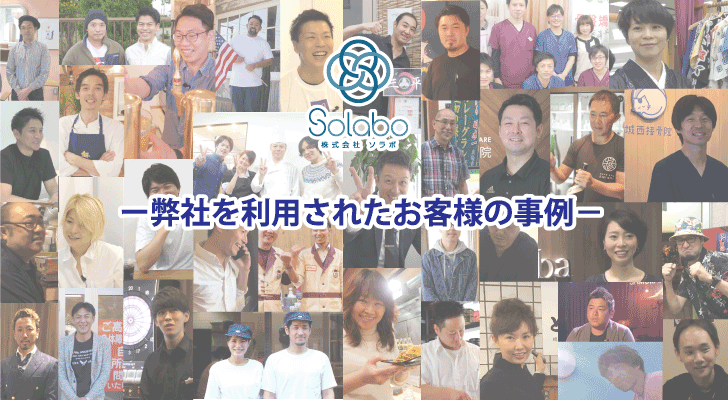コミュニティ運営という言葉をご存じでしょうか?
共通の関心を持つ人たちを集める「コミュニティ運営」は、企業とユーザーが双方向にやり取りのできるメリットが注目されています。
「コミュニティ運営をしたい!」と思ったら、どうすればいいのでしょうか。
今回は、コミュニティ運営とは何か、作り方からを成功させるコツまで、実際に株式会社SoLaboで行うコミュニティ運営事例についてもインタビュー取材を交えてご紹介します!
コミュニティ運営とは
コミュニティ運営とは、共通の関心を持つ人たちを集め、運営することを言います。
人々が寄せる興味関心の対象に、さまざまな目的や目標によって分化した膨大な数のコミュニティが存在し、活動(運営)が行われています。
身近な例では、学生時代に活動した部やクラブ、大学のサークル、学校の保護者の集まりのPTAなども、コミュティと呼べるでしょう。「コミュニティとは○○である」という明確な基準はなく、様々な形のコミュニティが日々、運営されています。
現在、企業が注目する「コミュニティ運営」に限れば、自社の製品やサービスを中心に、コミュニティをつくるケースが大半です。
コミュニティ運営のメリット
コミュニティ運営の、メリットをみていきましょう。
企業側のメリット:ユーザーの生の声を拾って自社製品・サービスに反映できる
ユーザー側のメリット:製品・サービスの要望を伝えて、利用時の不満が解消できる
企業にとって、コミュニティ運営の一番のメリットは「ユーザーの生の声を拾える」ことです。
コミュニティの中で「企業とユーザー」「ユーザーとユーザー」が交流をするため、ユーザーの要望や悩みを直に聞けます。加えてコミュニティに参加しているユーザーは当事者意識が高いため、質の高い、重要な意見を自社製品・サービスに反映できるでしょう。
ユーザーにも、コミュニティに参加するメリットはあります。まず自身の意見が企業に届きやすく、要望が反映されやすくなります。製品・サービスの利用時の不満が解消されると、嬉しいものです。また、コミュニティ内のユーザー同士で意見を交わし、情報共有やコミュニケーションもできるので、生活の質も向上させられるでしょう。
具体例として、ゲーム会社のケースをあげます。
ゲーム会社が1つのゲームタイトルのコミュニティを運営すれば、ユーザーから直接、ゲーム内容へのフィードバックや要望、製品化してほしいアイディアなど、得ることができます。新規ユーザーの質問に、コアユーザーが答えるなど、ユーザー同士の交流も深まりファンが増えるでしょう。結果としてゲーム自体のブランディングにつながるのです。
コミュニティ運営のデメリット
コミュニティ運営は企業とユーザーにとって得られるものがある活動です。一方でデメリットについても考えておきましょう。
まず「集客」です。近年では様々なコミュニティが運営されています。どこかで見たようなコミュニティを立ち上げても、競合他社が多く、思うように集客できないケースがあります。
次にコミュニティ立ち上げには「金銭的・人的コスト」が発生します。コミュニティ立ち上げ初期には入会案内やコミュニティ内での規則決め、イベントなどのコンテンツ制作といった作業が発生します。
またユーザーとの関係構築に時間がかかることもあります。特にこれまで自社と関わりのなかったユーザーを抱え込もうとするときには、一から関係を築かなければいけません。長期的な姿勢が大切です。
ただし、コミュニティ運営で生じるデメリットは企業側ものがほとんどで、ユーザー側のデメリットはほとんどありません。
企業側がしっかり対応すればユーザーに満足してもらえるコミュニティ運営を行うことができるはずです。
コミュニティのつくり方・運営の基本
コミュニティのつくり方や、運営の基本をおさえていきましょう。
コミュニティをつくるには「場所」と「刺激」が大切
コミュニティ運営をするためには、まず受け皿となるコミュニティをつくらなければなりません。コミュニティは「集う場所」があるから生まれるものなので、ユーザーを集められる「場所」が必要です。
物理的な場所でもいいですが、企業がコミュニティをつくるならオンラインのスペースをつくる方が管理しやすいでしょう。
コミュニティ用のwebサービスを一からつくるのもいいですが、手軽にはじめたいなら、既存のSNSを活用しましょう。FacebookのグループやYoutubeのオンラインサロンなど、情報をやり取りできる場所を設定します。「○○の話をするならここ!」とユーザーに所属意識が芽生え、積極的な参加を促すことができれば、それはひとつのコミュニティと呼べます。
また、コミュニティに所属してもダラダラしているだけでは、ユーザーのコミット力(物事に対して積極的に関わる姿勢)も低下します。場所を設定するだけでなく、交流を促す仕掛け、刺激を与えてコミュニティを活性化させましょう。
定期的に、ユーザー同士が合同で参加するイベント活動やミーティングなどを行い、ユーザーのやる気をアップさせる働きかけを継続することが大切です。
コミュニティ運営の基本「共通性を大切に」
コミュニティには、大きく2つの種類があります。主に誰でも参加できる「ライトコミュニティ」と、限られた人々の間だけが参加する「コアコミュニティ」です。
ライトコミュニティは無料で、コアコミュニティは有料で運営されることが多いです。
どちらのケースでも「集める人々に共通性を持たせ、共感を生み出すこと」はコミュニティ運営の基本です。目的や悩みが共通している人たちを集め、共感してもらうことこそが、ユーザーを満足させるよいコミュニティ運営につながるのです。
コミュニティ運営を成功させるコツ
ビジネスでのコミュニティ運営は、ただコミュニティを作って、何となく運営すれば成功するものでもありません。
企業が、初めてのコミュニティ運営でも成功させるコツは5つあります。
コツ1:コミュニティの目的をはっきり伝える
まず、企業はコミュニティをはじめる目的をユーザーに分かりやすく、はっきりと伝えるようにしましょう。
コミュニティを起こす理由は「ユーザーのニーズの把握」や「ユーザー同士の交流の場の構築」など様々です。コミュニティの目的をユーザーに明示しておかないと、「参加したのに思っていたのと違う」というミスマッチにつながってしまいます。
本当にコミュニティの目的に共感して参加してもらうためにも、目的はユーザーに明示しましょう。それが結果的に熱量のあるコミュニティへと成長するきっかけになります。
コツ2:社会につながるゴールを提示する
目的を持ったコミュニティ運営では必ずゴールがあります。そのゴールをユーザーにもわかる形で提示することで企業とユーザーの目的意識を統一することができ、ゴールに向かって一緒に進む足取りに一体感が出ます。
このゴールは少子高齢化や環境問題の解決といったスケールの大きなものである必要はありません。あくまでユーザー同士が共有している問題や悩みを解決することをゴールにすればいいのです。多くのユーザーが供給している問題や悩みは社会性を帯びていると言えるでしょう。問題や悩みを解決するゴールを設定することで、ユーザーは問題を自分事化できます。
コツ3:参加者同士で交流できる仕組みをつくる
ユーザー同士に交流ができる仕組みをつくることで、企業が1~10まで管理しなくてもコミュニティを適切な形で維持する効果が期待できます。
ユーザー同士で交流できれば、質問や疑問などを相談し合うなど、活発な交流が起き、コミュニティが疎遠になることなく、結束を強くする効果が期待できます。
コツ4:参加者に当事者意識を持ってもらう工夫をする
コミュニティ運営は企業だけの努力では成功しません。参加してくれるユーザーにも当事者意識を持ってコミュニティに参加してもらうことが大切です。
活発にユーザー同士でやり取りが発生すればそれだけコミュニティは盛り上がります。また、ユーザーの中から新たに参加者を呼び込んでもらうこともできるようになります。
ユーザーを巻き込むことがコミュニティ運営成功への秘訣です。
例えば、コミュニティ運営を行っていくと積極的に発言するユーザーと聞き役専門になっているユーザーに二分化することがあります。
そのようなとき、起業は聞き役専門のユーザーに働きかけて発言がしやすいようにサポートしてあげましょう。積極的に発言することで、当事者意識が芽生えることが期待できます。
コツ5:新規ユーザーが入りやすい環境をつくる
新規メンバーがコミュニティに入りやすい環境を用意することも、運営する企業にとっては重要な課題です。
コミュニティは立ち上げ時ばかりに目を向けがちですが、立ち上げ当初から参加しているユーザーしか盛り上がれないコミュニティは閉鎖的で、新規ユーザーの参加率の低下を招きます。もし、既存ユーザーが離脱してしまえばコミュニティはそれだけで立ちいかなくなります。
既存のユーザーを大切にしつつ、新規ユーザーに対する思いやりも忘れてはいけません。
よくわからないものに参加するのは怖いものです。コミュニティ内での活動やユーザーの声を積極的に発信していき、新規ユーザーが活動内容をイメージしやすいようにすれば、新規ユーザーも参加することに抵抗を感じにくくなります。
コミュニティ運営でやってはいけないこと
ここまでコミュニティ運営を成功させるコツをご紹介してきました。ここからはコミュニティ運営でやってはいけない3つのことについてお話しします。
(1)参加者を置いてきぼりにしない
コミュニティ運営を盛りあげるためには、それなりの熱量が必要です。しかし、企業側の熱量があまりに高すぎると、ユーザーはついていけずに、一歩引いて身構えてしまいます。
企業は、ユーザーや周囲の人々がきちんとついてきてくれているか、確認しながらコミュニティ運営を進めましょう。
(2)短期間で成果を得ようとしない
企業がコミュニティ運営を行うのはビジネスとしてなので、成果を求めることは当然と言えます。一方で、短期間で成果を追い求めるような運営をしてしまうと、企業とユーザーの想いが離れてしまい、ユーザーの離脱につながり、コミュニティが崩壊する可能性があります。
成果が表れるには時間がかかるということを念頭に、コミュニティ運営をしましょう。
(3)コミュニティ内での成果を過剰に意識しない
コミュニティの内容によっては、内々での成果に重点が置かれている場合もあります。しかし、自社のサービスを押し売りするような運営ではユーザーを惹きつけることはできません。
コミュニティは、ユーザーに企業の製品・サービスを提供する一方向のものではなく、企業とユーザーが一緒に企業の製品・サービスの価値をつくりあげていく双方向であるべきものです。
ユーザーと関わっていく中で、企業の製品・サービスの魅力、ひいては企業の魅力を知っていってもらうことを重視しましょう。
コミュニティ運営の実践例:株式会社SoLabo「士業進化論」
コミュニティ運営の実践例を見ていきましょう。
株式会社SoLaboでは「士業進化論」というコミュニティを運営しています。
| 1.目的 | 士業の皆様と一緒に「マーケティングの知識を高め合っていく」こと |
| 2.ゴール | 「士業のマーケティング力向上で日本を変える」 |
| 3.ユーザー | 士業の皆様 |
今回は株式会社SoLaboの田原広一氏にインタビューを行い、士業進化論とコミュニティ運営についてお話を伺いました。
参考|士業進化論

-本日はよろしくお願いいたします。まずは士業進化論がどういったものかについて教えてください。参加資格などは何かあるのでしょうか?
田原氏:マーケティングに興味関心がある士業の方であれば誰でもOKです。現在35名の士業の方に参加して頂いています。
-コミュニティの目的は「マーケティングの知識を高め合っていくこと」とうたっていますが、どのような狙いでコミュニティを立ち上げられたんですか?
田原氏:狙いは「士業の価値をマーケティングでアップデートすること」です。
士業はマーケティングに弱い方が非常に多い業界です。マーケティングの知識をもっと身につけることで、士業事務所が成長し、士業の価値が今以上にあがります。
そうなればさらに、士業の先生の顧問先にも、よい影響を与えます。
士業がマーケティングによって進化していけば、士業の顧問先にも良い影響がでて、顧問先企業も進化していきます。
士業を進化させれば、日本の起業家が進化し、日本が今よりももっと良くなる。だから、『士業進化論』と名付け、運営しています。
-なるほど。実際にどのように運営されているか、流れなどを教えていただけますか?
田原氏:毎月2回、イベントを実施しています。1回目は一話完結の講義です。2回目が講義に対する質問会ですね。
年間12回の講義、1年間勉強+実践+質問をすることで、マーケティングに強くなる。そういう仕組みです。
Facebookで交流もしています。でも特別こちらから交流を促すようなことはしていません。ちょっと気になったことがあったら質問や発信ができる場所というイメージしてもらえればわかりやすいでしょうか。
-なるほど。マーケティングに強くなる、とおっしゃいますが、具体的にはどのような状態を想像されているのでしょうか?
田原氏:士業の先生が何をすれば進化できるかをイメージでし、行動するためのタスクが出せる状態になることです。
また士業がマーケティングで騙されることがない世の中になってくれることですね。そうなってくれれば「士業進化論」のコミュニティ運営は成功です。
-士業進化論の運営に当たって、ここに気をつけている・大切にしているということはありますか?
田原氏:勉強するだけではなく、わからないことがあればすぐに行動に移して質問できるように、質問しやすい環境を整えています。
士業の方々は忙しく時間に余裕がない方もいらっしゃるので、動画化し、時間があるときに聞いてもらえる状況にしています。
-気軽に質問できるというのは安心感がありますね。実際にコミュニティ運営をしてみて感じる「コミュニティのよさ」のようなものはありますか?
田原氏:経営者視点では、やっぱり「何に悩んでいるかのユーザーの悩みを拾える」というのは大きいですね。先ほどお話ししたように毎月2回講義と質問回を実施しているので、参加者の状況が把握し、状況にあわせた話ができます。そして、その悩みにあわせた事業展開にもつなげられるんですよ。これはコミュニティ運営ならではのメリットだなと思います。
参加者視点では、質問回では誰かの質問と回答を聞くことで勉強でき、みんなで刺激を受けながら成長できる、というのが魅力だと言われますね。
個人的に感じる「コミュニティのよさ」は、セミナーを開いた後にはチャレンジしてくださる方の成長を実感できることですかね。普通に業務しているだけではわからないことなので貴重だなと思いますし、嬉しいです。

-士業進化論は、近い未来、どんなコミュニティになっていると考えますか?
田原氏:マーケティングを活用して進化したい!と考える士業の方々が集まり、参加者全員で刺激しあいながら参加者全員が成長している、と確信しています。
-士業進化論のほかにも株式会社SoLaboでコミュニティ運営をして盛りあげたい分野などはありますか?
田原氏:現在「創業大学」というコミュニティ運営を計画しています。創業するまでに学んでおいてほしいことをすべて提供し、参加者が互いに刺激しあい、参加者が創業することを目的としたコミュニティです。
-起業したい方に嬉しいコミュニティですね。最後にこれからコミュニティ運営をしようと考えられている方に、なにかアドバイスなどあればよろしくお願いいたします。
田原氏:コミュニティ運営には会費をどのように回収するか、利用規約はどうするか、毎回の告知、セミナー資料の準備など、大変なことはあります。
ですが、今回お答えしたように、得られるものは大きいです。
コミュニティ運営はご参加いただく方にも、運営する方にも、実りあるものです。
コミュニティでなければ得られない知見もたくさんあるので、ぜひビジネスでのコミュニティ運営にチャレンジしていただきたいです。