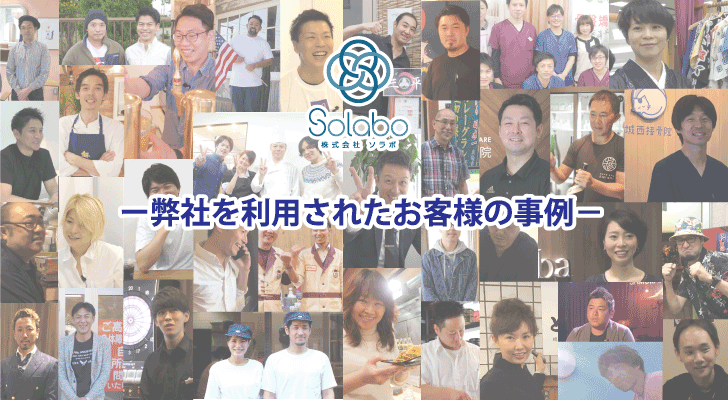飲食店を開業するとき重要となるのが、立地や見た目で集客のカギになる「店舗」。
しかしながら、近年では「店舗を持たない」飲食店が増えています。
今回は、店舗を持たない飲食店を開業する方法ついて解説します。
1.店舗を持たない飲食店とは
(1)店舗を持たない飲食店の営業方法
店舗を持たない飲食店とは、店舗以外の場所で飲食物を販売する営業方法を行う飲食サービス事業者のことです。
自宅やシェアオフィスなどの店舗以外の場所で調理し、料理配送サービスで配達してもらう手法や、キッチンカー(フードトラック)での移動販売といった店舗にあたる車両を利用する方法が代表的です。
店舗を持たない飲食店を開業する場合、通常の店舗営業と同じような営業方法は通用しない点に注意が必要です。店舗の前をふらっと通りかかり入ってもらうというようなことが期待できないため、サービスを多くの人に知ってもらう努力をしなくてはいけません。例えば、見栄えのよい商品写真をInstagramにアップするなど、SNSで積極的に情報発信する必要があります。
(2)店舗を持たない飲食店のメリット
メリット1:初期費用をおさえやすくスモールスタートに向いている
店舗を持たない飲食店は、当然ながら店舗を用意する必要がありません。内装工事費や店舗装飾などの店舗設置費用や店舗維持費が浮くため、比較的、初期費用をおさえやすいと言えるでしょう。
店舗を持たない飲食店は、小さく事業をはじめる「スモールスタート」に向いている業態です。
メリット2:立地によって売上が左右されにくい
店舗を持たない飲食店は、立地による影響が少ないです。
店舗を構えると、どうしても客層が「店舗周辺地域で暮らしている人々」に限定されます。
店舗を持たない飲食店の例で言えば、配達なら、お客さんが実際に足を運ばれるより、広い範囲の客層を取り込むことができるでしょう。移動販売なら、需要のある時間と場所を選んで効率よく販売を行えます。
飲食店の開業では、立地が非常に重要だと言われています。自店の商品にマッチした客層がいるエリアへ移れることが、店舗を持たない飲食店ならではの強みと言えるでしょう。
メリット3:間接的な費用をおさえて利益を生み出しやすい
コロナ禍で多くの飲食店で客足が遠のいている中、店舗を持たない飲食店は比較的安定して利益を生み出しやすいです。
まず、店舗にかかる賃料などの固定費がかからないことが大きいです。店舗を持たない飲食店はデリバリーやテイクアウトなどが中心のため、店舗の衛生管理コストも小さくなります。
間接的にかかる費用を削減し、収益に結びつけやすいやり方と言えるでしょう。
(3)店舗を持たない飲食店のデメリット
店舗を持たない飲食店を開業する上で考えられるデメリットを紹介します。
デメリット1:集客が大変
店舗を持たない飲食店の種類にもよりますが、まず、店舗がいつもそこにある訳ではないケースがほとんどです。店舗がある飲食店は、通りかかれば常に意識してもらえますが、店舗を持たない飲食店は見えないも同然です。
インターネットの店舗情報を見つけてもらい、店舗の実態が伝わるようにしなければ集客ができません。
お店専用のSNSを開設し、商品の写真やお店の情報をこまめに発信するなど、積極的に広告を打つ必要があります。
デメリット2:配達・販売ルート確保に費用がかかる
店舗を持たない飲食店は、配達サービスの利用料や、移動販売用のキッチンカーの準備といった配達・販売ルート確保には、人件費や手数料などの費用がかかります。
例えば、Uber Eats(ウーバーイーツ)ならデリバリーサービスの手数料として売上総額の35%が必要と言われています。
2.店舗を持たない飲食店の種類と開業方法

店舗を持たない飲食店にはいくつか種類があります。(1)ゴーストレストラン、(2)キッチンカー(フードトラック)、(3)自宅カフェ・週末カフェ(ソーシャルダイニング)、(4)コンテナハウス が代表的です。
それぞれの説明、開業方法についても見ていきましょう。
(1)ゴーストレストラン
ゴーストレストランとは
ゴーストレストランとは、ゴーストキッチンとも呼ばれるアメリカ発の飲食店の形態で、簡単にいえばデリバリー専用飲食店です。
自宅やレンタルオフィス、シェアキッチンなどで調理をし、配達サービスを利用して配達を行います。
店舗がなくとも調理場所のキッチンさえ用意できれば始められるので、初期投資金額が少なく、従業員・スタッフが少なくても、こだわった料理が提供できるのが強みです。
半面、店舗がないために「たまたまお客さんの目に入って来店」といったことは期待できないので、集客・宣伝に力を入れる必要があります。
また、お客さんと接触することがないので、お客さんからのフィードバックを得られず、モチベーションが上がりにくい、といった課題もあります。
ゴーストレストランの開業に必要なものと手続き
開業に必要なものの例
|
開業に必要な手続きの例
| ・飲食店営業許可の取得 飲食店を営業するためには「飲食店営業許可」が必要になります。これは地域の保健所の窓口やホームページで取得方法を確認してみてください。・食品衛生責任者の資格の取得 上記の「飲食店営業許可」を取得するためには食品衛生責任者を最低1名はおかなければいけません。食品衛生責任者となるためには講習を受講し、合格する必要があります。 ・デリバリーサービスへの登録 |
(2)キッチンカー(フードトラック)
キッチンカー(フードトラック)とは
キッチンカーとは、フードトラックと呼ばれる、調理場として使える設備を搭載し、移動販売を行う車両、あるいは移動販売サービスのことです。
キッチンカーの準備が必要なので一見大変そうですが、販売を行うときだけレンタルすることもできるので、実は簡単に始められます。
好きな時に売り上げが見込める場所を選んで販売できるので、需要が大きくなる昼時だけ稼働したり、イベントの日だけ出店したり、効率よく売上につなげるスケジューリングがしやすい利点があります。
出店場所ごとに販売許可や保健所の営業許可をとる必要があるので、許可申請が大変なことには注意しましょう。
2021年6月より食品衛生法が改正され、キッチンカーの営業許可にも大きく影響します。
これまでキッチンカーによる営業許可には「飲食店営業」「菓子製造業」「喫茶店業」の3つに分かれていましたが、法改正後は「飲食店営業」に一本化されます。
また全国でバラバラだったキッチンカーに必要とされる設備も統一化されます。
これからキッチンカーで開業されようとしている方は改正後の法律について少し調べておきましょう。
食品衛生法の改正については厚生労働省のホームページから確認することができます。
参考:厚生労働省|食品衛生法の改正について
これからキッチンカーをはじめられる方は、ハウス食品によるキッチンカーレンタルサービス「街角ステージweledi」をチェックするのをおすすめします。
キッチンカーや仕込み場所、販売場所をレンタルすることができるサービスです。売上の30%が引かれ、現在はまだ都内でしか展開されていませんが、初期投資がないため、初めて飲食業にチャレンジされる方にとっては心強いサービスになることでしょう。
参考:街角ステージweldi
キッチンカー(フードトラック)の開業に必要なものと手続き
開業に必要なものの例
|
開業に必要な手続きの例
| ・飲食店営業許可の取得 飲食店営業許可は調理加工を行う施設に付与されます。キッチンカーならキッチンカー1台に付与されるという形で、2台以上のキッチンカーを所有するのであれば、2つ分、飲食店営業許可が必要です。・食品衛生責任者の資格の取得 上記の「飲食店営業許可」を取得するためには食品衛生責任者を最低1名はおかなければいけません。食品衛生責任者となるためには講習を受講し、合格する必要があります。 ・食品営業自動車or食品移動自動車のどちらかの取得 |
(3)自宅カフェ・週末カフェ(ソーシャルダイニング)
自宅カフェ・週末カフェ(ソーシャルダイニング)とは
自宅カフェとは、週末カフェとも呼ばれる、副業として本業がない日のみ自宅の一部を利用して飲食店を経営する方法です。
厳密には店舗が必要となりますが、自宅を使うので、既に自宅を持つ人にとっては初期投資額が安くすみます。
自宅を使うため、セキュリティや近隣トラブルなど、通常の飲食店では起きにくい問題も増える可能性があります。特に近隣住民への説明や告知はしっかりしておきましょう。
ソーシャルダイニングとは、自宅などの個人の家以外にも定休日の飲食店店舗、シェアオフィスなどを活用して単発の料理イベントを開催する飲食店経営の方法です。
非常に手軽で、ソーシャルダイニング専用のサービスをしている会社もあるほど、近年では人気を集めています。
本業としてよりも、副業として手軽に営業したい場合におすすめです。
自宅カフェ・週末カフェ(ソーシャルダイニング)の開業に必要なものと手続き
開業に必要なものの例
|
開業に必要な手続きの例
|
(4)コンテナハウス
コンテナハウスとは
コンテナハウスとは、飲食店に限定した場合、店舗準備も引っ越しも楽なコンテナハウスで営業する方法、またはそのコンテナハウスの店舗のことです。
厳密にはコンテナハウスという店舗を持っていますが、建物ごと移動できるコンテナハウスであれば資金が少なくて済む以外に、撤退や移動も楽なので、立地面でのリスクを低く経営できるのが利点です。
コンテナハウスを専門に扱う業者もいるので、手を出しやすく、立地が読みづらい今の飲食店経営に向いている形態のひとつと言えるでしょう。
難点としては、通常の店舗と比較し、外観が標準タイプだと目を引きにくく、集客につながりにくい点です。集客のために内装や外観にこだわると、コンテナハウス自体にかかる資金が少なめとはいえ、通常の店舗並みに投資が必要になってしまうので、予算はきっちり決めておきましょう。
コンテナハウスの開業に必要なものと手続き
開業に必要なものの例
|
開業に必要な手続きの例
防火管理者とは、火災による被害を防ぐために消防計画を作成し、防火管理を行う者で、30名以上収容できる規模の施設であれば、必ず選定しなければいけません。 |
まとめ
店舗を持たない飲食店を開業する方法を解説しました。
ゴーストレストランやキッチンカーなど、効率よく営業すれば大きな利益を上げられる可能性が高く、今後、飲食店の主流となる可能性を秘めています。
それぞれの飲食店の特性を理解し、自分にあったビジネスモデルの飲食店を開業しましょう!