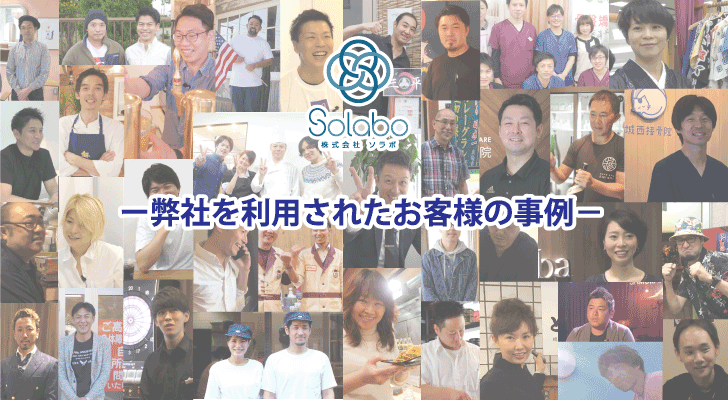近年、日本人の働き方は変化していると言えるでしょう。以前は新卒で入った会社で定年まで勤めあげ、老後は退職金と年金で暮らしていく事が一般的でした。
しかし、その働き方は既に崩壊しています。今回の記事で提案したいのは、会社が自分そして家族のために退職金を用意しておくと会社の節税になるという事例です。
退職金なしの会社が多い!最近の経営事情とは
老後の資金として企業に勤めている多くの方が頼りにしている退職金ですが、実は法律で社員に必ず与えなければいけないものとして決められてはいません。事実、従業員数50人以下の会社の7%は退職金なしというデータが日本の行政機関である人事院の調査で明らかにされています。
日本には約380万もの中小企業がありますが、そのうちの85%(製造業以外)は従業員数が5人以下といういわゆる「自営業」の方々です。彼らは会社勤めをしている訳ではないので、そもそも退職金制度がありません。企業年金も厚生年金には加入していないため、国民年金のみで支給額も低くなってしまいます。
しかし、自分で経営しているということは逆に考えると「自分で退職金制度を作ればいい」という発想が可能なのです。
老後のために会社化で節税しよう
自営業の方は個人事業主として経営している場合と会社を設立して経営している場合の2パターンがあります。もしあなたが個人事業主なのであれば、節税という意味で少し損をしている部分があります。なぜなら、会社(企業)の場合は退職金を「損金」として計上することが税法上で認められていますが、個人事業主の場合はそれができないからです。
「損金」とは、会社が得た利益から差し引いても良い費用です。
次の項目でその仕組みについて詳しく解説しましょう。
役員退職金の会計処理
あなたが事業主で家族経営をしている場合、あなたと家族が受け取る退職金は「役員退職金」と言います。退職をする際に一時的に支払われる退職金は、通常、以下のように計算されます。

最終役員報酬とは、経営者が退職前に最後に受け取る給与のことです。また、功績倍率とは、同業・類似規模の他法人における功績倍率を参照して当てはめるのですが、役員の場合は2~3倍が妥当とされています。
【功績倍率の例】
| ステイタス | 功績倍率 |
| 創業社長 | 3 |
| 2代目以降社長 | 2.5 |
| 取締役 | 2 |
例えば、あなたが30年働いて退職前に50万円の役員報酬を受け取り、功績倍率は3倍の場合は以下の退職金額となります。
あなたの役員退職金(4,500万円)=50万円×30年×3倍
退職金は4,500万円です。欲を出して、この計算式を超える1億円などの法外な金額にすると「損金不算入」となってしまいますので要注意です。
退職金4,500万円があれば、老後の蓄えとして助かりますよね。但し、まずはそれぐらい事業で稼がないといけないのが大前提です。しかし、企業に勤めてこれだけの退職金がもらえるか、または自力で売り上げを上げて自分に退職金を上げるか、どちらが現実味をもつか考えてみるのも良いのではないでしょうか。
退職金受取時には所得税がかかる
あなたが退職して役員退職金を受け取る際には、個人の所得としてみなされます。これを税法上では退職所得と呼びます。退職所得は老後の生活費として認められているため、相続税などよりも低めの税率となっています。
(退職金の額-退職所得控除)×1/2=退職所得
退職所得×税率=所得税
上記の例と同じ条件で、退職金にかかる所得税を計算してみましょう。
(4,500万円-退職所得控除)×1/2=退職所得
※勤続年数5年以下は×1/2は不可
退職所得×税率=所得税
ここで分からないのは退職所得控除というワードです。退職所得控除は他の控除と同じく、「税金を計算する際にこの金額を差し引いても良いよ」という金額で条件によって金額は異なります。以下の表を参照してください。
【退職所得控除】
| 勤続年数(Work=W) | 退職所得控除 |
| 20年以下 | 40万円×W
(80万円に満たない場合は、80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(W-20年) |
上記の例では、勤続年数30年でしたので
800万円+70万円×(30-20年)=8,700
と、なりました。退職所得控除額は8,700万円です。この額を元の式に戻しましょう。
(4,500万円-8,700万円)×1/2=2,100万円
この2,100万円を以下の式に当てはめます。
退職所得(2,100万円)×税率=所得税
ここでまた分からないのは税率というワードです。退職所得の税率については、以下の表をご参照ください。
【平成30年分所得税の税額畳】
| A 課税退職所得金額 | B 税率 | C 控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
2,100万円は下から2行目の40%の税率を掛けますので、
退職所得(2,100万円)×40%=840万円
所得税は840万円となりました。4,500万円から840万円を差し引くと、4,500万円の81%である3,660万円が手元に残る計算です。2割は税金で持っていかれますが、その前に会社で損金として計上している際に節税できていますので、負担は実際にはより軽くなります。
まとめ
「退職金がなくても、年金で生きていける」と考える成人の方が現在、日本にはどれほどいるでしょうか?年金額は年を追うごとに減少しています。そこで一つの方法として、個人事業主ではなく会社設立をして事業を行い、退職金を損金として計上するやり方があります。