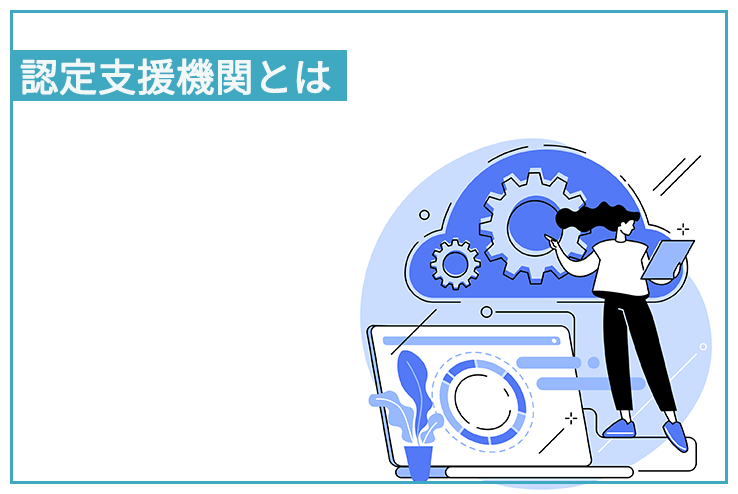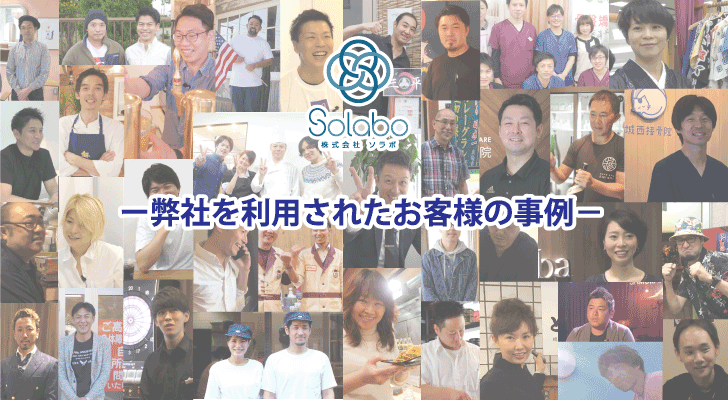中小企業の経営者にとって資金調達は常に悩みの種でしょう。経営者にとって、国から出る補助金の活用は、大切な資金調達手段です。
様々な補助金がある中で、設備投資を通じて労働生産性の向上を支援する「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」(通称:ものづくり補助金)をご存知ですか?
「ものづくり補助金」には、経営者だけでは作成できない申請書類があります。
「認定支援機関確認書」です。この記事では、認定支援機関確認書とは何か、どうすれば入手できるのかをご説明します。
1.補助金とは?
中小企業の経営者にとって国からの出る補助金は、重要な資金調達の一つです。
補助金は、国の政策ごとに目的や趣旨が異なります。
補助金の募集要項を満たして申請し、審査を受けます。審査を通過(採択)したら、補助金の対象となる事業を実施し、報告書などの必要書類を提出し、検査を受けます。
そこで承認され、初めて補助金を受けることができます。
必ずしも全ての経費が補助金の交付対象になるわけではありません。補助金や事業内容によっては、事業全部あるいは一部の経費をまかなうことができます。
ものづくり補助金とは?
補助金の中でも、注目されているのが「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」(通称:ものづくり補助金)です。
対象は日本国内に本社と実施場所(工場や店舗など)を持つ中小企業・個人事業主で、業種は製造業や卸売業、小売業、サービス業などと間口が広くとられています。
特に、平成30年度の補助金では、中小企業の固定資産税を減免する「生産性向上特別措置法」に基づいて、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る「先端設備導入計画」の認定を受けた企業に対し、補助率を引き上げる措置を採用しました。
条件によっては補助上限額1,000万円、補助率は3分の2以内で設備投資ができるとあって、関心が集まりました。
補助金についてもっと詳しく知りたい方は、中小企業庁ウェブサイトの公募要項をご確認ください。
中小企業庁ウェブサイト >> 1.ものづくり・商業・サービス革新を支援します >> ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
2.認定支援機関確認書とは?どうやって入手する?
ものづくり補助金の申請をするときは「認定支援機関確認書」という書類を作成し、事業計画書等と一緒に提出する必要があります。
「認定支援機関確認書」は、それ以外の申請書類を揃え、「経営革新等支援機関」に依頼すれば入手できます。
経営革新等支援機関とは、国の認定を受けた、商工会議所・商工会・金融機関などの機関や、税理士・公認会計士・弁護士・中小企業診断士などの人のことです。
経営革新等支援機関という認定支援機関が「ものづくり補助金の申請書類の内容を確認しましたよ」という確認の文書を「認定支援機関確認書」と呼びます。
税務・金融・財務などに詳しい、経営に関係する者以外の第三者のチェックが必要ということです。
認定支援機関について詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
3.認定支援機関の選び方
依頼すれば「認定支援機関確認書」が手に入るといっても、認定支援機関をどう選べばよいのか迷うこともあるでしょう。
認定支援機関はその種別で、相談・支援できる分野が異なります。
例えば、同じ書類の確認でも、税制度に詳しい税理士と、法律に詳しい弁護士では気にするポイント、見る観点が違います。
つまり、得意とする分野が違うということです。
重ねて、これまでのものづくり補助金における認定支援機関の役割は「認定支援機関確認書」の作成だけでしたが、採択後のフォローアップも必須となりました。
補助金は、報告し、その内容が受理されなければ受け取ることができません。報告事務処理を含め、事業計画・目標の実現のために協力者が必要です。
そういった観点からいえば「認定支援機関確認書」は、税務に慣れている専門家、報告書などの事務処理に慣れている専門家、補助金の金額が大きい場合は金融の専門家にサポートしてもらうのがよいでしょう。
税務に慣れている専門家の筆頭は税理士です。ものづくり補助金は、固定資産税の優遇措置が含まれています。補助金と節税は税務処理上で密接に関係しているため、税理士にサポートしてもらうと心強いでしょう。
報告の事務処理に慣れている専門家の筆頭は、税理士と行政書士です。
補助金の金額が大きい場合は、銀行など、金融の専門家に依頼するのもよいでしょう。基本、補助金は使った後の後払いで受け取ります。事業で使う資金が大きい場合、融資を受ける場合があります。自社の積極的な動きを知ってもらうことで、金融機関の融資担当との良好な関係構築につながり、後々の資金調達で有効に働く場合があります。
ただし、採択後は依頼した金融機関から補助金の融資を受けることを前提になるため、予め融資条件などは比較した上で依頼するのがよいでしょう。
また、銀行などの金融機関の場合、報告事務処理などのサポートはしていない場合もあります。予め確認しましょう。
まとめ
ものづくり補助金に限らず、補助金は申請し、報告するまでのスケジューリングが肝心です。
報告の事務処理が滞ったため、採択されたのに補助金が受けられなくなってしまった…なんてことにならないように、認定支援機関と二人三脚での事業計画の遂行が求められています。
「認定支援機関確認書」は補助金のサポート実績を確認するのはもちろん、得意分野も確認し、信頼できる経営革新等支援機関に依頼するようにしましょう。