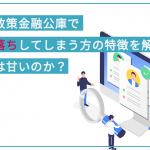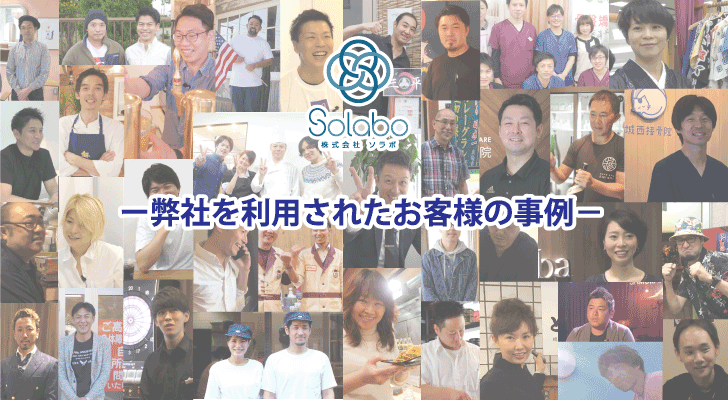「ブラック企業」「長時間残業」という言葉が日々ニュースで使われているように、日本の会社員を取り巻く環境は今決して明るいとは言えません。さらに、アメリカやイギリスなど他国と比べ日本の起業率は半分以下と非常に低いため、最近は日本政府による起業のあっせんが盛んに行われています。
「このまま会社員は耐えられない、独立しよう。」と考えるあなたへ。この記事では退職後に必要な手続きや挨拶などの必要な準備についてまとめていきます。
1.会社の辞め時を考えてから逆算して準備する
①いつが会社の辞め時か?
会社の辞め時はは人によってさまざまですが、あなたが以下の状況であれば独立を考えてもよいかもしれません。
【会社の辞め時タイミングリスト】
- 会社を辞めたいと2年以上悩んでいる
- パワハラや違法残業で身体や精神が壊れかけている
- 今の会社でできることは全てしたとやりきった感がある
- 今の会社でポジションについているが、この先のキャリアパスが見込めない
- 自分や周りができることは全てしたが、どうしても状況は改善しない
- 会社の経営方針の変更で、今までの働き方と大きく変わることが決定した
②一番大切なのは生活費の確保
「退職して翌月から給与が入らなくても生きていけるのか?」これが一番重要です。何はなくとも、生活するだけのお金はやはり必要です。独立してもお金がない生活で、「こんなことなら会社辞めなきゃよかった」と後悔しても遅いのです。
【(参考)独立時の資金の目安】
- 自分名義の預貯金が200~300万円以上ある
- 定期的な不動産収入がある
- 会社からの給料がなくても半年~1年は暮らしていける
- リボ払いやキャッシングで借金まみれではない
- 家賃が必要ない(実家暮らしまたは住宅ローン完済)
独立前にやっておくべきことは、毎月のご自身の生活費の把握です。生活費とは、住居費・光熱費・水道代・NHK受信料金・通信費・食費の固定費と交際費・外食費・旅行費用・趣味に使うお金の変動費を言います。Money Forward Me(マネーフォワードミー)というアプリを使えば、毎月どの項目にいくら使っているのが一目でグラフ化されるのでオススメです。
※上記URLをクリックすると、他社サイトへリンクします
独立してすぐに利益を出すのは大変です。預貯金の切り崩しだけでなく、預貯金以外に定期的にお金が入ってくるシステムを作っておくのが重要です。ブログ収入でもいいですが、ひたすらブログを書くのも大変ですよね。
現実的なところで投資信託は手軽で経済感覚も付くのでオススメです。投資信託は10年~20年単位で放っておく気持ちで運用しましょう。会社員時代に毎月少額からでもいいので始めておけば、景気変動時に当たれば仕込んだ投信が大きな収益を生む可能性があります。
③家族や同僚や友人への相談

「会社辞めようと思うんだ」と家族や親しい友人・知人には前もって伝えておきます。その際にアドバイスを受け、「やっぱり会社辞めるの、止めよう」と思って踏みとどまるのもアリです。一度会社を辞めようと思いだすと、なかなか辞めるのを止めるという思考にはいきつかないものです。
しかし、会社は辞めるのがゴールではありません。その先に長く続く人生を生き抜かなければいけません。「会社の辞め時」って存在します。間違えると、あとから修正するのは大変です。
④事業資金の資金調達

会社を辞めて独立する決心がついたら、事業資金について考えましょう。本気で独立して生活したいなら、手元に資金がないとどうにもなりません。これまでの常識では、事業用のお金を調達するには「融資」または「自分の貯金を使う」「家族から借りる」といった方法がスタンダードでした。
しかし、現在ではこの他にもクラウドファンディングや助成金・補助金などの選択肢も増えています。簡単な違いは以下の通りです。
- 事業融資:事業用のお金を金融機関などから利子付きで借りること(お金の目安:200万円~2,000万円)
- クラウドファンディング:事業用のお金を一般の個人などからリターン(グッズや利子など)付きまたは無償で得ること(お金の目安:数千円~数百万円)
- 助成金・補助金:一定のルールに乗っ取った資金をあなたが使った場合に受けられる公的なキャッシュバック(お金の目安:10万円~500万円)
確実に資金調達をしたいのであれば、一番上の事業融資が良いでしょう。何故なら、クラウドファンディングはネットが得意な方やプロジェクトが共感を得やすいものであれば成功しますが、非常に個人差のある資金調達法だからです。また、助成金・補助金は基本的にキャッシュバックなので、最初にお金を集めるのには適していません。
2.会社員退職時に必要な手続き

①上司に相談する~退職日の決定
会社員を辞めることを決めたら、まずは上司に相談です。退職日の目安はあなたの属する業種や役職にもよります。まず最低ラインは1か月後です。しかし、これはアルバイトレベルの話です。
今あなたが大手チェーン店の店長をしている、事務職で定期的に任されている仕事があるのであれば引継ぎ期間が必要です。だいたい半年後の退職を目途に考えておきましょう。
②仕事の引継ぎと有給消化について

会社退職日が決まったら、仕事の引継ぎを計画的に行います。あなたの仕事を誰に引き継げばいいかを上司に相談し、本業の妨げにならぬよう次期後任者へ引き継ぎをします。必要なデータ(客様情報や特別な事情など)はできるだけ文書でも作成し共有しておきます。
また、有給が残り何日あるのかを確認します。最後まで消化させない会社、有給消化を見越して実際の退職日を早く設定する会社などいろいろあります。上司や総務担当者にあらかじめ確認しておきましょう。
③会社からの貸与物(制服・IDカードなど)や保険証の返還
健康保険証や社員証・IDカードなど会社から借りているものがたくさんあることでしょう。退職日に誰に減却すればいいのか、あらかじめ担当者へ確認しておきます。
④雇用保険被保険者証を受け取る
失業保険をもらうためには、雇用保険被保険者証というピンク文字で書かれた白い用紙が必要となります。経理や総務をしている方などに確認しましょう。
⑤挨拶
終わり良ければすべて良し。今いる会社の人と、この後また会う可能性もゼロではありません。また、独立後に一緒に働く仲間にもなるかもしれません。できる限り感じよい挨拶を心がけましょう。自分の部署だけでも、菓子折りなどの品を持っていくと好感度も上がります。
3.独立開業するための準備をしよう

①お金がない時は無理に事務所や会社を設立しない
自己資金があまりない中で、会社設立で不動産を借りると固定費や初期費用が大幅にアップします。お金がない時はお金を貯めるか、または事務所なしで自宅から開業するなどできるだけお金をかけない方法を考えましょう。
②開業時期を決める
開業時期は業種にもよりますが、半年後~1年後を目指して動きましょう。必要な資格や許認可があれば取る。お金が足りなければ合間にアルバイトをする。必要な知識がなければ勉強する。他業種の研究をする。仕入れ先について調べる、などやるべきことは無数にあります。
③融資に申し込む
開業時期を決めたら、融資についても検討します。融資の際に、物件が必要な業種(飲食店など)まず物件契約をしていないと融資がおりないので、その点は注意してください。
融資については、以下の記事も是非ご覧ください。
④必要な仕入れや工事を発注する
飲食店であればテーブルや看板や厨房など、学習塾であれば教材やホワイトボードなどの必要な備品などを発注しましょう。資金が少ないのであれば、少ない資金でどのようにやりくりするのかも事業主であるあなたの腕の見せ所です。
まとめ
独立して開業する際に必要な手続きについて簡単にご説明いたしました。独立は会社と違い、資金の準備や保険なども全部自分でしなくてはいけないので大変です。
しかし、会社員とは違う自由ややりがいがあるのは確かです。独立を成功するには、とにかく準備をしっかりすることです。