個人事業主として独立開業したい人や既に独立開業しているひとのなかには、事業資金の調達を検討している人もいるでしょう。資金調達の経験がなく、どのような方法が自分に適しているのかわからないという人もいますよね。
当記事では、個人事業主が資金調達する方法を解説します。資金調達方法を選ぶ際に気をつけたい点も解説するので、資金調達を検討している個人事業主の人は参考にしてみましょう。
目次
個人事業主の資金調達方法
個人事業主が資金調達する方法は「もらう」と「資産を現金化する」と「借りる」の3パターンに分類できます。自分で貯めたお金だけでは事業資金が足りない人は、いずれかから資金調達方法を検討しましょう。
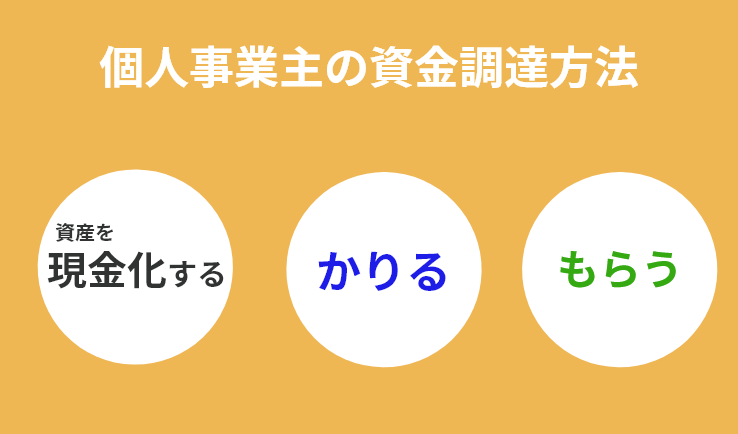
| 分類 | 資金調達方法の例 | 特徴と注意点 |
|---|---|---|
| もらう | ・補助金や助成金制度を利用する ・クラウドファンディングをおこなう |
調達したお金は返済不要。補助金や助成金は後からの入金になるため、調達に時間がかかる。クラウドファンディングは資金調達までの時間が読めない点に注意が必要 |
| 資産を現金化する | ・ファクタリングを利用する | 売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらう。利用時はファクタリング会社へ1%~20%の手数料を支払う必要がある |
| 借りる | ・金融機関から融資を受ける ・自治体の制度融資を利用する ・ビジネスローンで借りる |
一定の条件を満たしたうえで審査に通過する必要がある。借りたお金の返済と利子の支払いが発生するため、返済時に負担がかかる |
お金をもらう方法として、補助金や助成金、クラウドファンディングなどが挙げられます。いずれの方法もお金を受領するだけで、返済不要である点がメリットです。
補助金や助成金は設備や物品購入後に後からお金が支給されるため、必要なタイミングでお金がもらえないデメリットがあります。
クラウドファンディングの場合は支援者を集められるだけの認知度やアイデアの新規性が求められるうえ、資金調達までの時間が読めないというデメリットがあります。
資産を現金化する方法としてファクタリングが挙げられます。ファクタリングは利用する際に手数料がかかる上、現金化するためには売掛債権を保有している必要があるため、独立開業して間もない個人事業主は利用しにくい傾向があります。
お金を借りる方法として、銀行や信用金庫などの金融機関からの融資や、自治体の制度融資、ビジネスローンが挙げられます。融資を受けるためには、一定の条件を満たす必要がありますが、金融機関や自治体によっては独立開業したばかりで実績のない個人事業主にも融資をおこなう場合があります。
ただし、お金を「借りる」方法を選んだ場合には、借りたお金の返済と利子の支払いが発生するため、返済の負担がかかる点がデメリットです。そのため、お金を借りて資金調達したい人は金利などの情報から返済負担の程度を比較して検討しましょう。
なお、当サイトでは金融機関からの融資や利用できる補助金など、現状の経営状況や開業準備からいくらの資金調達ができるか無料診断ができます。
資金調達を検討する際は入金までの時間も確認する
資金調達方法によって入金までにかかる時間は異なるため、資金調達方法を検討する人は申し込みから入金までにかかる時間も確認するようにしましょう。
資金調達方法によっては、入金のタイミングが資金繰りに間に合わなくなり、資金ショートを引き起こす可能性があるためです。
| 資金調達手段 | 入金までにかかる時間の目安 |
|---|---|
| 金融機関から融資を受ける | 1週間から2か月 |
| ビジネスローンで借りる | 即日から1週間 |
| ファクタリングを利用する | 即日から5日間 |
| クラウドファンディングをおこなう | プロジェクト実施機関によって異なる |
| 補助金や助成金制度を利用する | 制度によって異なる |
※上記の時間はあくまで目安のため、実際に利用する際は変動する可能性があります
銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受ける場合、ビジネスローンよりも入金までにかかる時間は長くなりますが、金融機関の融資はビジネスローンよりも金利が低いため、返済の負担は抑えることができます。
なお、資金が必要になった段階で銀行や信用金庫などの金融機関に申し込んでも、入金に時間がかかる場合は資金繰りには間に合いません。
そのため、個人事業主として独立した人はいつどの程度の資金が必要になるのかを把握するために「資金繰り表」を作成し、事前に銀行や信用金庫などの金融機関に融資の相談をしておくのがよいでしょう。
資金繰り表の作成方法を知りたい人は「資金繰り表とは?経営者のための資金繰り表の活用法と作り方」も参考にしてみてください。
金融機関から融資を受ける
個人事業主の資金調達方法のひとつに、銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受ける手段があります。一口に金融機関の融資といっても利用する金融機関や融資制度によって申し込みできる人の条件や金利なども異なるため、それぞれの特徴をおさえておきましょう。
| 主な融資の種類 | 特徴 | 金利(実質年率)の目安※ |
| 銀行融資 | 都市銀行や地方銀行から直接融資を受ける方法。独立開業して間もない個人事業主は融資を受けにくい | 1%~3% |
| 信用金庫の融資 | 地域に根差した金融機関であるため、特定の地域で事業をおこなう個人事業主は利用しやすい | 1%~5% |
| 制度融資 | 地方自治体と民間金融機関と信用保証協会の3機関が連携して実行する融資。はじめて融資を利用する個人事業主でも融資を受けやすい | 1%~3% |
| 日本政策金融公庫の融資 | 政府系金融機関で、個人事業主を含めた創業者向けの融資制度を設けている。創業時に無担保無保証で融資を受けられるため代表者のリスクが抑えられる | 1%~3% |
※金利相場はあくまで目安です。実際の金利は金融機関や申込者の状況によって異なります
融資を受けるためには、各金融機関などが定めた利用条件を満たしたうえで、所定の審査に通過する必要があります。
審査に通過できるかの基準は金融機関によって異なりますが、申込時に提出する必要書類の内容や金融機関の担当者との面談から総合的に判断されるため、融資を受けたい人は金融機関の担当者に必要書類を確認するようにしましょう。
個人事業主として銀行や信用金庫などの金融機関から創業融資を受ける方法を知りたい人は「個人事業主が創業融資を受けるには」も参考にしてみてください。
ビジネスローンを利用する
個人事業主の資金調達方法のひとつにビジネスローンがあります。ビジネスローンとは銀行のほか信販会社や消費者金融などが提供する、事業資金に特化した金融商品です。
ビジネスローンは即日~1週間程度で融資を受けられるため、緊急性の高い資金調達手段として利用されます。
一方で、ビジネスローンの実質年率は15.0%前後で設定されており、金融機関からの融資と比べて利息の負担は大きいです。そのため、ビジネスローンの継続的な利用は資金繰りをかえって悪化させる恐れがあります。
また、ビジネスローンの借入残高があると、銀行や信用金庫などの金融機関からの融資審査に通過しにくくなる場合があります。返済の目途がたっていることを前提に、緊急性の高い資金繰りをしなければならない時のみビジネスローンの利用を検討しましょう。
ビジネスローンの利用を検討している人は「資金調達方法の一つとしてビジネスローンを利用するべきか?」も参考にしてみてください。
補助金や助成金制度を利用する
個人事業主の資金調達方法のひとつに国や地方自治体などから支給される補助金と助成金があります。補助金と助成金は返済不要のお金ですが、先にお金をもらえるのではなく、お金を支払った後にその分が入金される仕組みです。
補助金と助成金のメリットは融資のように元本の返済や利息の支払いが発生しない点です。
一方で、入金までにかかる時間が融資よりも長いというデメリットがあります。そのため、補助金と助成金を検討している人は受給までの資金繰りが滞らないかどうかを確認する必要があります。
| 補助金 | 採択件数が決められているため、審査に通過した場合のみ受給できる |
| 助成金 | 審査はなく、定められている要件を満たしている場合は受給できる |
個人事業主が使える助成金や補助金の例を挙げると、「雇用調整助成金」「キャリアアップ助成金」などの従業員の雇用やキャリアに関する助成金や「小規模事業者持続化補助金」のような販路開拓や生産性向上の取り組みを支援するための補助金などがあります。
なお、対象者の条件によって利用できる補助金と助成金は異なるうえ、制度によっては公募時期が設定されているため、応募できる時期が限られている場合もあります。
補助金と助成金を検討している人は、中小企業庁が運営する中小企業向け補助金・総合支援サイトの「ミラサポplus」から支援制度を探してみましょう。
東京都内で創業する人には創業助成金を利用する選択肢もある
東京都内で創業する人は創業初期の経費として利用できる「創業助成金」の制度を利用して事業資金を調達するのも選択肢のひとつです。
創業助成金は公益財団法人東京都中小企業振興公社が、都内での創業を具体的に計画している個人事業主や創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす人に事業資金を助成する制度です。
助成金額は100万円から300万円までと限られていますが、賃借料、広告費、器具備品購入費、従業員人件費などの幅広い費用項目に利用できます。
創業助成金は年に2回、4月と10月に募集期間を設けており、募集開始の1か月ほど前から募集要項などの情報が告知されます。詳細な募集スケジュールを知りたい人は東京都創業NETの公式サイトを確認しておきましょう。
クラウドファンディングをおこなう
個人事業主の資金調達方法のひとつにクラウドファンディングがあります。クラウドファンディングは、インターネット上でお金を出してくれる支援者を募るサービスです。
現在、さまざまなクラウドファンディングサービスがありますが、支援金額に応じて支援者に返礼品などのリターンを返す方式が主流です。
クラウドファンディングは広報やPR活動がうまくいけば、目標の資金を集めることができますが、プロジェクトに対する認知を得られなければ資金が集まらずに失敗することもあります。
そのため、事前の準備時間を確保したうえで斬新なアイデアを打ち出せるかどうかがプロジェクトの成功を左右します。
また、プロジェクトが成功し目標の資金を集められた場合でも、その後の支援者への御礼の連絡やプロジェクトの関する進捗報告などにある程度の時間を割く必要があります。
リソースを考えたうえで計画立てて進めていくことが重要なため、クラウドファンディングを検討している人はスケジュールと計画をまとめたうえで、サービス会社に問い合わせてみるのがよいでしょう。
クラウドファンディングのやり方を知りたい人は「クラウドファンディングのやり方は?参加方法と条件を解説」も参考にしてみてください。
ファクタリングを利用する
個人事業主の資金調達方法のひとつにファクタリングがあります。ファクタリングは、商品やサービスを提供した際に発生する売掛債権をファクタリング会社に売却することで資金調達する手法です。
たとえば、100万円の売掛債権がある場合、ファクタリングを利用することで100万円から手数料分を差し引いた金額をファクタリング会社から調達することができます。
ファクタリングサービスによって手数料は異なりますが、売掛金に対して1%~20%の幅の手数料が設定されています。
手数料が20%なら、100万円の売掛債権に対して20万円が手数料として差し引かれるため、手元に残るお金は80万円になります。ファクタリングを検討する人はファクタリング会社に見積もりを依頼し、手数料を比較しておきましょう。
また、ファクタリングを繰り返し利用すると、その回数分の利益が目減りしてしまい、結果として資金繰りの悪化を招く可能性があります。そのため、ファクタリングは予期せず運転資金が不足した場合の一時的な資金調達手段と捉えておきましょう。
災害時や経済危機が発生した場合は国や自治体の制度も検討する
災害や経済危機などの緊急事態によって、資金繰りが悪化した場合は国や自治体の制度も検討しましょう。
大規模な災害発生時や経済環境が著しく変化し、財務大臣や農林水産大臣、経済産業大臣による危機認定がなされた際には、政府の指定した金融機関が中小企業や個人事業主に特別貸付などの支援策を実施する場合があります。
たとえば、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した個人事業主に対して、政府系金融機関である日本政策金融公庫は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を実施しています。
業績に関する一定の要件を満たしている個人事業主は、この制度を利用することで無担保かつ実質無利子の融資を受けられます。
また、経済産業省は金融庁・財務省と連携して「中小企業活性化パッケージNEXT」を策定し、経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援を拡充することを発表しました。これにより、新型コロナの無利子無担保融資は9月末申し込み分で終了になりましたが、日本政策金融公庫の「スーパー低利・無担保融資」を2023年3月末まで継続することがわかっています。
新型コロナウイルス感染症特別貸付の利用を検討している人は「コロナの影響が理由でも日本政策金融公庫から融資が受けられない人の条件 審査に落ちる理由とは?」も参考にしてみてください。
まとめ
個人事業主が資金調達する方法には「もらう」と「資産を現金化する」と「借りる」の3パターンがあります。業歴や事業の業績によって適切な資金調達方法は異なるため、資金調達方法を検討する際はそれぞれの利点や注意点を比較してから決定しましょう。
とくに、独立開業して間もない個人事業主の場合には、お金を借りるのが難しいのではと考える人もいますが、実績の乏しい個人事業主が利用できる融資もあります。
創業時でも日本政策金融公庫の新規開業資金や、地方自治体と金融機関と信用保証協会の3機関がおこなう制度融資を利用できる可能性があるため、創業のために運転資金や設備資金の融資を受けたい人は検討してみましょう。




