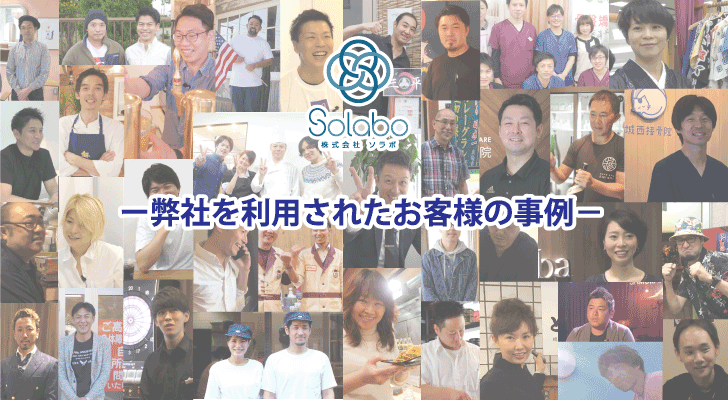確定申告は財務に関わる大切な基本なので、しっかりポイントを押さえておく必要があるでしょう。
特に押さえておきたいのが法人と個人事業主の違い。確定申告では法人か個人かで必要な手続きや申告する税金の種類、必要書類や期日など様々な面で違いが出てきます。
この記事では確定申告における法人と個人の違いと、状況に応じて法人と個人、どちらの方が効率的かを解説しています。ぜひ起業する際に参考にしてください。
1.法人と個人事業主の確定申告の違い
法人と個人事業主の確定申告の違いについて、まずは簡単にそれぞれの特徴を表にまとめましたので見てみましょう。
| 個人事業主 | 法人 | |
| 対象の税金 | 3種類 所得税・消費税・復興特別支援税 |
5種類 法人税・消費税・都道府県民税・市町村民税・法人事業税 |
| 手続き書類 | 白色申告2種類 青色申告3種類 |
8種類 |
| 申告期限 | 翌年2月16日~3月15日 | 決算から二か月間 |
(1)法人と個人事業主は納める税金が異なる
まずは支払う税の種類の違いです。
申告が必要な税は主に3種類(所得税・消費税・復興特別支援税)の個人事業主に対して、法人では5種類(法人税・消費税・都道府県民税・市町村民税・法人事業税)の税金を申告する必要があります。
これは、法人の場合は個人では申告の必要がなかった自治体に支払う地方税も申告しなければならないことが大きい理由となります。
また、個人事業主の場合は事業の所得(売上-経費)=事業主個人の所得として計算され、所得税が課税されますが、会社の場合は事業所得には法人税が課税され、会社が支払った給与や役員報酬といった個人に渡されるお金には、別途所得税がかかります。
このように事業所得と個人の所得が分かれて計算される、という点が法人と個人事業主の最大の違いと言えるかもしれません。
とはいえ法人の場合の個人にかかる所得税の処理は年末調整という形で行うため、確定申告とは別の作業です。
ちなみに社員個人の年間の給与所得が2,000万円を超えてしまうと、年末調整ではなくその社員個人が確定申告をしなければならなくなってしまう点は覚えておきましょう。
(2)法人と個人事業主は必要書類が異なる
申告する税金の量が増えるだけあって、法人では必要書類も増えます。
個人事業主の必要書類
| 書類名 | 内容 | 提出先 |
| 確定申告書B | 白色申告・青色申告どちらでも必須の申告書 |
税務署 |
| 収支内訳書 | 白色申告の場合に提出する収支の内訳を書いた書類 | |
| 青色申告決算書 | 青色申告の場合に提出する収支の詳細を書いた決算書 | |
| 青色申告承認申請書 | 青色申告にする場合に開業届と同時、または青色申告対象年の3月15日までに提出する書類
例:2020年の分を2021年に確定申告する場合、2020年3月15日が期限 |
法人の必要書類
| 書類名 | 内容 | 提出先 |
| 総勘定元帳 | すべての取引や経理処理が科目ごとに記録された元帳 | 税務署 |
| 領収書綴り | 経費の領収書を日付順に綴ったもの | |
| 決算報告書 | 会社の損益、貸借などのデータをまとめた報告書 | |
| 法人事情概況説明書 | 事業内容や従業員数をまとめた書類 | |
| 法人税の申告書 | 税務計算書類、勘定科目明細書、決算申告書等を綴ったもの | |
| 消費税の申告書 | 消費税額の計算書、確定申告書等を綴ったもの | |
| 地方法人税の申告書 | 地方法人税の計算書と申告書。事務所や店舗が複数ある場合その数分割申告が必要。 | 都道府県民事務所、
管轄自治体の役所 |
| 税務代理権限証書 | 税理士に決算を委託するための書類 | 各申告書に添付 |
個人の場合は青色申告の場合のみ、簿記の記録をはじめとした帳簿を7年間の保管が必要となります。
法人の場合はただ単に種類が増えるだけでなく、証拠となる領収書やデータそのものも提出しなければならない上、それらの書類は原則紙に印刷したうえで10年間保管しなければなりません。
(3)法人と個人事業主では確定申告の時期が異なる
また、もう一つ重要なのが納付期日で、個人が毎年2月16日~3月15日と決まっているのに対し、法人の場合は定款によって決算期日を自由に決められるため、企業ごとに定めた決算から2カ月以内に納付する、という形になっています。
これは、個人の場合は1月1日から12月31日までとなっている課税時期そのものが、法人の場合は定款で定めた一年間になるため、その期の終わりに決算、それからの申告となるためです。
決算終了日から納付日まで、作業は法人の方が多いにもかかわらず、日数も法人の方が少ないので、直前になって慌てることがないよう、コツコツと日頃から書類を作成しておくといいでしょう。
個人事業主
| 課税の対象 | 課税対象期間 | 申告期限(※2) | |
| 所得税 | 事業所得 | 事業年度
(1月1日~12月31日) |
翌年2月16日~3月15日 |
| 消費税
(※1) |
課税売上高 | 翌年3月31日まで |
法人
| 課税の対象 | 課税対象期間 | 申告期限(※2) | |
| 所得税 | 役員報酬等 | 定款にて定める事業年度 | 事業年度終了日(決算日)から2ヶ月以内 |
| 法人税 | 事業所得 | ||
| 消費税
(※1) |
課税売上高 |
※1.前々年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税。ただし、資本金または出資金の額が1,000万円以上の場合は課税。また特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合も課税。特定期間は、個人事業者の場合は前年1月1日から6月30日まで、法人の場合は前事業年度開始日以後6ヶ月の間
※2.期日が土日と重なる場合は繰り下げ
2.個人事業主の確定申告
個人事業主が確定申告の対象となる税金は、「所得税」「消費税」「復興特別所得税」の3つです。ちなみに所得税は「所得」(売上-経費)に対してかかる税金で、消費税は「売上」そのものに対してかかる税金となります。
消費税は、二年前の課税売上高が1000万円以下かつ一年前の上半期の課税売上高が1000万円以下ならば支払いの義務が免除されます。つまり、その一定額にさえ到達しなければ消費税は無視することができます。
「復興特別所得税」は平成25年1月1日から平成49年(2036年)12月31日までの間、所得税の源泉徴収の際、源泉徴収額の2.1%が徴収されることになっています。「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」という法律によって定められています。
この他に「住民税」「国民健康保険税(保険料)」「事業税」もありますが、所得税を申告すれば都道府県や市区町村から納付額が通知されるので確定申告する必要はありません。
肝心の申告方法は、比較的簡単な表記で終わることができる白色申告と、決算作業に少し手間がかかるものの、税金に控除が受けられるほか、様々な特典を得られる青色申告の二種類があります。
個人事業主の確定申告は、法人ほど複雑ではありませんが、書類作成に手間がかかるところも多いため、一人で手続きを完了できるか不安であれば、税理士に依頼するのも選択肢のひとつです。
(1)白色申告で確定申告する流れ
①記帳作業
日々の取引の情報を記帳していきます。
一気に書き込むのでは膨大な手間になってしまうので、日頃からコツコツとその日の取引を書き込んでいくのがいいでしょう。
②決算作業
棚卸表を作成し、その情報をもとに滅科償却を行って決算をしていきます。
滅価償却とは、固定資産の価値が年数の経過により落ちていくことを計算したもので、この減少分を必要経費として計算することができるというものです
「定額法」という計算方法で算出し、毎月同じだけ価値を減らしていくものとして計算していきます。
③収支内訳書の作成
収支内訳書を作成していきます。
収支内訳書はこれまでの記帳内容、棚卸に関する情報、滅価償却費をまとめるもので、今までの計算で出した情報を一つにまとめることで課税される所得金額の根拠を明らかにするだけでなく、事業内容全体を把握しやすくすることもできます。
④確定申告書を作成
収支内訳書を見ながら確定申告書を作成していきます。
確定申告書は国税庁のホームページに掲載されており、印刷すればすぐ使えるほか、「確定申告書等作製コーナー」というページがあり、そこで簡単に作成できるため利用してみるといいでしょう。
(2)青色申告で確定申告する流れ
基本的な流れは白色申告とほぼ同じ
日々の記帳を行い、決算処理をして確定申告書を作成するという基本的な流れは白色申告とほぼ同じです。
ただし、青色申告で確定申告をするためには、青色申告承認申請書を税務署へ届け出る必要があります。
期日は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。(初年度のみ)
二年目以降は取り消さない限り自動的に継続されるため、再度提出する必要はありません。
創業時から青色申告にしたい場合は創業と同時に提出すれば切り替えの期限は無視できるので、覚えておくといいでしょう。
また、記帳方法に「複式簿記」という方法を使うことが必須となります。
複式簿記は習得が難しいものの、より正確で不正がしにくい記述方法となっているため、青色申告ではこの方法を使わなければなりません。
簿記の知識がないという方でも専用の会計ソフトを使用することで簡単に帳簿の作成ができます。なお、「節税対策をしたい」「将来に備え、資金調達を考えている」など、状況に応じて税理士に頼んでやってもらうことも検討するとよいでしょう。
青色申告には特典がある
青色申告で使用される複式簿記には先述の通り正確で不正がしにくいというメリットがあり、政府も青色申告の方を推奨しています。
そのため、青色申告では白色申告と比較して最大65万円の控除や損失の繰り越し、家族の雇用などが可能となる大きな特典が与えられています。
青色申告のメリットを詳しく知りたい方は「青色申告すると受けられる9つのメリットとは?」をご一読ください。
3.法人の確定申告
法人の場合、正確には「決算申告」と呼ばれ、確定申告とは別のものとなります。決算申告では各税金を申告する前に「申告書」を作成しなければなりません。
決算申告の対象となる税金は、「法人税」「消費税」「都道府県民税」「市町村民税」「法人事業税」の5つです。このうち法人税と消費税は税務署に申告しますが、他の3つは法人が存在する自治体の県税事務所や市役所等で申告することになります。
ちなみに、本社と違う自治体に事業所が存在する場合にはその事業所の自治体にそれぞれ申告が必要です。
申告・納税の期限は事業年度終了の日から2か月以内ですが、申告の提出が間に合わない場合、法人税など一部の申告については特定の要件を満たして手続きすれば最大1か月の猶予がもらえます。
ただし、納付期限は遅れると延滞税が課せらますので、期限までに見込納付を行い、申告後還付を受けるケースが多いです。
(1)法人の確定申告の流れ
①決算の整理・仕訳
決算整理・仕訳を済ませなければ法人税の額を確定できません。
最初に処理をして法人税の額を確定させましょう。
決算のために日頃から伝票や帳簿をしっかり作っておくと作業が楽になります。
②消費税の申告書を作成
法人税を確定させた後は消費税の額を確定させます。
消費税は資本金又は出資額が1,000万円以下、かつ二期前の一年間、及び一期前の上半期の売上が1,000万円を下回っていれば支払いが免除されます。しっかりと確認しておきましょう。
また、消費税の支払額次第では「中間申告」といって来年度に年度途中で消費税の支払いが発生する可能性があります。具体的には国に治める消費税が48万円をこえた場合に中間申告の義務が発生します。こちらも気が付かずに支払いが遅れてしまうと問題になるので、確定申告時に確認が必要です。
③勘定科目の内訳・明細書の作成
上記に並行して、勘定科目の内訳・明細書を作成します。
作成には時間、労力ともに大きく必要となるので日頃から内訳明細書の作成を意識して帳簿を管理していきましょう。
④法人税の申告書を作成
法人税の申告書を作成します。法人税の申告書は複数あり、「別表一( 各事業年度の所得に係る申告書)」「別表二(同族会社などの半手理に関する明細書)」「別表四(所得の金額の計算に関する明細書)」「別表五(一)(利益積立金額及び資本金などの額の計算に関する明細書)」「別表五(二)(租税公課の納付状況などに関する明細書)」などはどの会社でも必要となるため重要です。
別表にはほかにもさまざまな種類があり、処理や手続きも複雑なのでここから先は一般的に税理士にやってもらうことになります。
⑤市町村民税・都道府県民税の申告書を作成
市町村民税、都道府県民税は「法人税割」と呼ばれる法人税に一定の税率をかけることで算出される税金です。また、正確には法人税に一定の税率をかけた上で、会社規模に応じた一定額を納める均等割という計算も加えて算出されます。
市町村民税、都道府県民税の申告書は会計ソフトでは作成できないため、自分で作成するか税理士に作成してもらうことになります。
⑥決算処理
法人税・事業税・特別法人事業税・都道府県民税・市町村民税を費用とし、損益計算書の負債として貸借対照表に計上、算出します。
⑦残高計算表を完成させる
決算処理が完了した時点で、最後に残高試算表を完成させます。残高試算表は、各勘定科目の残高を一覧にした表のことです。
⑧法人税の申告書を完成させる
完成した残高試算表と照らし合わせつつ法人税の申告書をチェックしていきます。間違いがないことを確認したら法人税の申告書の完成です。
ちなみに、この作業で作成した書類は10年間の保管義務があるので、しっかりとコピーを取って保管しておきましょう。
参考:帳簿書類等の保存期間及び保存方法(国税庁ホームページ)
まとめ
法人と個人事業主の確定申告の大きな違いを「申告する税の種類」「提出する書類の数」「申告する時期」の観点から解説してきました。
法人となれば手続きや書類作成など、複雑な手間が生じますので、現在個人事業主として事業を行っている方は、消費税の支払いが免除される所得1,000万円ラインを超えそうになったタイミングで法人に切り替える「法人成り」を検討するのが節税にはベストのタイミングです。
法人成りをした一期目は法人の事業所得が800万円以下なら法人税も税率15%に抑えられるなど、うまく調整をすれば大きな節税につながります。
ただし、法人成りをした場合、その年の社長の確定申告は個人事業主としての事業所得と会社役員としての給与所得両方に対して行わなければなりません。
自分がどんな税金を払わなければならないのか、どんな作業をしなければならないかを考えながら、個人事業主と法人、どちらの方がいいかを考えていきましょう。