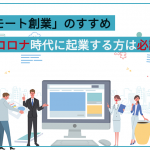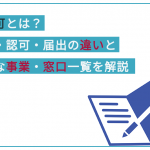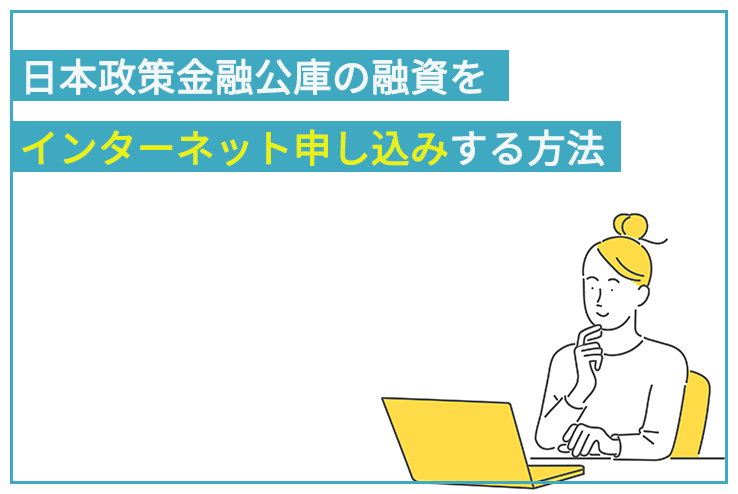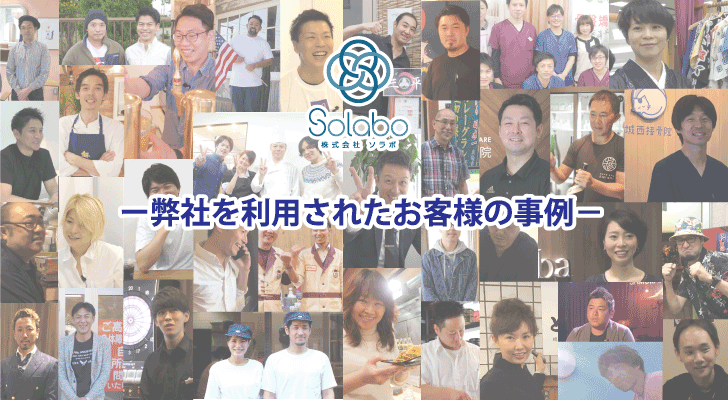2020年より転換したWithコロナ時代の流れ、新しい生活様式(ニューノーマル)としてリモートワークの普及、あらゆるもののオンラインサービス展開が目立ちました。同様に起業のあり方も変わりつつあります。
今回は、新しい創業のあり方として、ビジネスモデルも届出などの事業手続きも「リモート」を前提とした持続可能な経営を目指して起業する「リモート創業」を提案します。
リモート創業のメリット・デメリット、リモート創業をするにはどうすればよいか、創業〜事業経営で必要な事業手続きのオンライン対応状況の一覧もご紹介します。リモートで事業をスタートしたい方はぜひ参考にしてください。
創業を考えている方、コロナ禍で経営に不安がある方は、国が認めた経営問題に関する相談・支援をする認定支援機関の株式会社SoLabo(ソラボ)にぜひご相談ください。経営アドバイスから、融資(ローン)に必要な書類の作成、審査の進行管理や面談対策まで、事業者向けの経営サポートを行っております。
Withコロナ時代の起業のあり方「リモート創業」
Withコロナ時代の起業事情をご紹介しながら、キーワードとして新しい起業のあり方「リモート創業」をご提案します。
リモート創業とは
リモート創業とは、ビジネスモデルや事業手続きについて、リモートを前提にした持続可能な事業経営を目指して起業する、という株式会社SoLabo(ソラボ)が提案する新しい起業のあり方です。
「リモートワーク」という、会社などの本来働く場所から離れて(remote)働く(work)働き方が浸透しました。人との接触を最低限にしたビジネスモデルは「非対面型ビジネスモデル」(非接触型ビジネスモデル)と呼ばれ、必須要件になりつつあります。
「リモートワーク」も「非対面型ビジネスモデル」も、ITやweb、オンラインサービスの普及と活用によって実現できるようになったものです。
今、起業のあり方も変わりつつあります。その変化は「リモート創業」と呼べる、事業の場所やあるべき姿など、固定観念から離れた(remote)自由な発想での起業だと考えています。
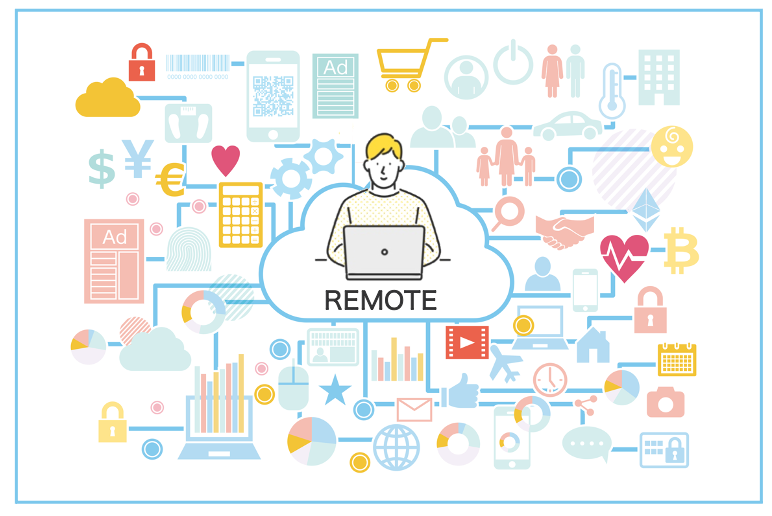
地元に戻って創業する「Uターン創業」や、今まで住んだことのない場所での創業「Iターン創業」をする人も珍しくありません。
リモート創業するには?
リモートワークを前提に非対面型ビジネスモデルをつくる
リモート創業するには、まずは自由にビジネスモデルを考えましょう!
そもそも創業とは、事業を創って笑顔の人を増やすことなので、ビジネスの核となるような利益を出す仕組み、つまりビジネスモデルがないとはじめられません。
なお、創業とは何か、ビジネスモデルの作り方については次を参考にしてください。
ある程度、ビジネスモデルが固まったら、リモートワークやオンラインサービスなどを組みあわせて、人との接触が少ない「非対面型ビジネスモデル」になるよう工夫しましょう。
ただし「その場にいることに価値のある」業種や業務の場合、非対面型ビジネスモデルにするのは難しいです。非対面型ビジネスモデルが難しいと、リモート創業に向いていないと言えるでしょう。リモート創業に向いていない業種・業務は「リモートワークに向いていない」ケースとほぼ同じですので、詳しくは次の記事をご覧ください。
リモート創業に向いていようが、向いていなかろうが、「当たり前」と思っている固定観念を捨てて、柔軟な発想で考えるのも大切です。全ての業務をリモートワークにできなくとも、手続きをオンラインサービスで行ったり、一部業務を非対面型にしたりはできるでしょう。
また、事務所をシェアオフィスで構えたり、飲食業なら店舗を持たないあり方を検討したり、など「何が本当に必要なものなのか」を見極めて選択しましょう。
リモート創業で失敗しないためにできること
リモート創業で失敗しないためにできることをまとめると次の通りです。
- ビジネスモデルをみがいて進化させ続ける
- 新しいことをはじめても、手段と目的を混同せず、割り切って活用する
- 最低限、経営判断できる程度にITやwebに関する情報を追うようにする
リモート創業では、「手段」であるはずのリモートワークや非対面型ビジネスモデル、オンラインでの事業手続きなどを「目的」としてこだわってしまうと失敗するリスクがあります。
一度決めたビジネスモデルでも、状況によって柔軟に変え、常にビジネスモデルをみがいて進化させ続けるのが、時代を問わず、望ましい経営のあり方といえるでしょう。
リモート創業のメリット・デメリット
状況によっては当てはまらないケースもありますが、リモート創業のメリット・デメリットをまとめると次の通りです。
リモート創業のメリット
- 持続可能なビジネスモデルで、資金調達しやすい
- 柔軟な働き方で、優秀な人材を確保しやすい
- 事業継続に必要なものだけにコストを割ける
リモート創業のデメリット
- 普通に創業するケースよりも論拠を固める必要がある
- リモート創業に向かない業種や業務もある
- 経営者のITの素養によって事業の成長が左右されやすい
基本的に、リモート創業は常識的な事業経営から自由な発想で創業することになるため、その将来性に賛同してもらえれば、内外の味方ができやすいといえます。
「名を捨てて実をとる」という慣用句のように、当たり前の体裁にこだわらず、内容や利益を選ぶことになるので、事業継続に必要なものだけの選択と集中できるのも利点です。
一方で、リモート創業は、ビジネスモデルを理解してもらうために、普通に創業するケースより細かく論拠を求められるでしょう。
また、現状はリモート創業に向かない業種・業務もありますが、今後、IT技術の進化や社会情勢の変化で変わることも予想されます。経営者のITの素養によって事業の成長が決まる面もあるので、できるだけ最新IT事情を追って「今、何がリモートでできるようになっているか」はおさえておきましょう。
創業〜事業経営で必要な事業手続きのオンライン対応状況
オンライン手続き(電子申請)を活用しよう
リモート創業としては、事業手続きがオンラインでできるものは、オンライン手続きにしてしまうのが理想的です。
官公庁のオンライン手続きは、一般的に電子申請と呼ばれます。電子申請は、官公庁の管轄によってオンライン手続きをするシステムが変わることがあるので、注意が必要です。
また、システムを利用する前に利用条件や環境をよく調べましょう。ICカードリーダライタやマイナンバーカード、事前の利用者アカウントの取得手続きが必要なこともあります。
電子申請で代表的なものは3つあります。
- 「e-Tax」(イータックス):国税を納付する用
- 「eLTAX」(エルタックス):地方税を納付する用
- 「e-Gov」(イーガブ):納税以外の行政機関への申請用
「e-Tax」(イータックス):国税を納付する用
国税電子申告・納税システム「e-Tax」(イータックス)を初めて利用する場合、手続きの前に「e-Taxの開始届出書」を提出する必要があります。
e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて|e-Tax
「eLTAX」(エルタックス):地方税を納付する用
地方税ポータルシステム「eLTAX」(エルタックス)は、e-Taxと字面が似ていますが、全く別物です。eLTAXも利用するなら届出が必要なので、利用の流れを確認しておきましょう。
「e-Gov」(イーガブ):納税以外の行政機関への申請用
納税以外の行政機関の申請は「e-Gov」(イーガブ)で行えます。具体的には、厚生労働省、国土交通省、金融庁、経済産業省などです。利用には登録し、アプリケーションをインストールする必要があります。
続いて、必要な事業手続きと、オンライン対応(2021年春時点)を見ていきましょう。オンライン対応状況を調査した結果、基本的に、汎用性の高いもの、手続き頻度が高いものはオンラインで手続きできる傾向がみられました。
なお、必要な事業手続きには、大きく3つの種類があります。
- 創業で必要な手続き
- 業種によっては必要な許認可の手続き
- 毎年必要な事業手続き
①[創業手続き]のオンライン対応
創業手続きは、個人事業主で創業するか、法人で創業するかによっても変わります。
個人事業主
| 提出書類 | 対象・条件・期限 | 提出先 | オンライン対応 | 対応の根拠 |
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 個人事業主が開業するとき、開始日から1ヶ月以内に提出する | 税務署 |
可(e-Tax) |
個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき|国税庁
ページ下部に〈e-Taxを利用してオンラインで申請・届出ができます。〉と書かれている
|
| 所得税の青色申告承認申請書 | 個人事業主が青色申告するために、事業開始した日から2ヶ月以内に提出する | 税務署 |
法人
| 提出書類 | 対象・条件・期限 | 提出先 | オンライン対応 | 対応の根拠 |
| 法人設立届出書 | 法人設立の日(設立登記の日)以後2ヶ月以内に提出する | 税務署 | 可(e-Tax) | 個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき|国税庁
ページ下部に〈e-Taxを利用してオンラインで申請・届出ができます。〉と書かれている
|
| 青色申告の承認申請書 | 会社設立後3ヶ月または第1期事業年度終了日のいずれか早い方の前日までに提出する | 税務署 | ||
| 法人設立設置届出書 | 会社設立後、速やかに提出する(申請書類のフォーマット例|東京都主税局)
*提出先によってフォーマットや期限などが異なる |
都道県税事務所または市町村役場 |
可(eLTAX) |
電子申請・届出とは|eLTAX地方税ポータルシステム
ページ中ほどの「利用可能な標準様式一覧」に書かれている |
なお、創業の手続きはシステムが違うと手続きも変わってしまうため、基本は1回きりの手続きなのに大変です。
内閣府・総務省・厚生労働省が主管のオンラインサービス「マイナポータル」で「法人設立ワンストップサービス」を利用すれば、システムを気にせずに手続きできます。
法人設立ワンストップサービスで行える手続き
○ 国税・地方税に関する設立届
※ 利用可能な国税関連手続一覧は下記参照
○ 雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)
などの法人設立後に必要な全ての行政手続
※ 法人設立ワンストップサービスでは、「かんたん問診」の質問事項に答えていくことで、利用者のみなさまに必要な手続が表示されます。
引用元:法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました|国税庁
②[業種によっては必要な許認可の手続き]のオンライン対応
業種によっては許認可が必要なことがあるので、手続きしましょう。許認可とは何か詳しく知りたい方は関連記事をご参照ください。
- 許可:法律で禁止される行為を、国や地方自治体に書類を提出し、できるようにする。法律で定められた基準を満たしていれば、必ず許可がおりる。
- 認可:国や地方自治体が、事業者からの申請があったとき、ある一定の基準を満たしているのを認める。認可の基準を満たしていれば、必ず認可される。
- 登録:国や地方自治体に書類を提出し、帳簿に記載してもらう。
- 免許:特定の資格を持った者に権利や地位を与える。
許認可は一回きりのためか、ほぼオンライン手続きに対応していません。なお、ご紹介する一覧のオンライン手続き可否は、当サイトを運営する株式会社SoLabo(ソラボ)が提出先に対し、電話で確認をとっています(2021年春時点での調査)。
許認可の手続きのオンライン対応一覧表 *クリックすると下に情報が表示されます
| 許認可・届出名称 | 業種 | できるようになること |
許認可の種類 |
提出先 | 根拠となる法律 |
オンライン対応 |
| 飲食店営業 | 飲食店業 | レストラン経営 | 許可 | 保健所 | 食品衛生法施行令第35条 | 不可 |
| 喫茶店営業 | 飲食店業 | レストラン経営
(2021年6月から飲食店営業に統合される) |
許可 | 保健所 | 食品衛生法施行令第35条 | 不可 |
| 菓子製造業 | 飲食店業 | レストラン経営 | 許可 | 保健所 | 食品衛生法施行令第35条 | 不可 |
| 美容所開設届 | 美容業 | 美容室の経営 | 届出 | 保健所 | 美容師法 | 不可 |
| 理容所開設届 | 理容業 | 理容室の経営 | 届出 | 保健所 | 理容師法 | 不可 |
| 旅館業営業許可申請 | 旅館業 | 宿泊料を受けて人を宿泊させる旅館の経営 | 許可 | 保健所 | 旅館業法 | 不可 |
| 開設届 | クリーニング業 | クリーニング店の経営 | 届出 | 保健所 | クリーニング業法 | 不可 |
| 営業届(無店舗取) | クリーニング業 | クリーニング店の経営 | 届出 | 保健所 | クリーニング業法 | 不可 |
| 興行場営業許可申請 | 興行場運営業 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などの施設運営 | 許可 | 保健所 | 興行場法 | 不可 |
| 墓地等経営許可申請 | 墓地経営業 | 墓地等の経営や管理 | 許可 | 保健所 | 埋葬法 | 不可 |
| 建設業の許可 | 建設業 | 建設工事の請負、建設会社の経営 | 許可 | 都道府県 | 建築業法 | 不可 |
| 宅地建物取引業免許申請 | 宅地建物取引業 | 不動産業のうち売買や仲介といった取引 | 免許 | 都道府県 | 宅地建物取引業法 | 不可 |
| 一般廃棄物処理業許可 | 一般産業廃棄物処理業 | 事業活動に伴って生じた廃油、廃酸、廃アルカリなどの廃棄物を適正に処理 | 許可 | 都道府県 | 廃棄物処理法 | 不可 |
| 貸金業登録制度 | 貸金業 | 事業者や消費者を対象への融資(銀行などを除く) | 登録 | 都道府県 | 貸金業法 | 不可 |
| 第一種医薬品製造販売業/第二種医薬品製造販売業 | 医薬品製造販売業 | 自社で開発した医薬品や他に委託して製造した自社の医薬品などを販売
*許可種別によってできる業務が変わる |
許可 | 都道府県 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 不可 |
| 第1種旅行業/第2種旅行業/第3種旅行業/地域限定旅行業 | 旅行業 | 海外・国内の旅行関連業務
*登録種別によって旅行区域を限定される |
登録 | 観光庁 | 旅行業法 | 不可 |
| 電気工事業登録 | 電気工事業 | 送電線、配電盤などの電気工事 | 登録 | 都道府県 | 電気事業法 | 不可 |
| 風俗営業許可 | 風俗営業 | 麻雀、ラウンジ、パチンコ、ゲームセンター・キャバレー・クラブなどを経営 | 許可 | 警察署 | 風俗営業法 | 不可 |
| 古物商許可 | 中古品販売業 | リサイクルショップなど中古の衣類や貴金属などの販売 | 許可 | 警察署 | 古物営業法 | 不可 |
| 警備業の認定申請 | 警備業 | 警察業務とは異なり、利用者の依頼と費用負担により依頼者の生命・身体・財産を守ること | 認定 (公安委員会) |
警察署 | 警備業法 | 不可 |
| 質屋営業許可申請 | 質屋業 | 物品を質に取り、金銭を貸し付ける営業 | 許可 | 警察署 | 質屋営業法 | 不可 |
| 酒類の販売業免許 | 酒類販売業 | 酒類の販売、酒屋経営 | 免許 | 税務署 | 酒税法 | 一部可(*1) |
| 職業紹介業許可 | 職業紹介業 | 人材の紹介 | 許可 | 公共職業安定所 | 職業安定法 | 不可 (*2) |
| 米穀類販売業開始届 | 米穀類販売業 | 米や雑穀の精米販売 | 登録 | 市町村 | 新食糧法 | 不可 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業許可 | 一般貸切旅客自動車運送事業 | タクシー、観光バスなどの運行 | 許可 | 運輸局 | 道路運送法 | 不可 |
*1:国税庁管轄の酒税法に関わる一部手続きがe-Taxで対応可
*2:制度上は申請できるが、オンラインで正確な書類を提出することが現状困難との電話回答あり
③[毎年必要な事業手続き]のオンライン対応
創業した年も含め、毎年、決まった頻度で必要な事業手続きもあります。
毎年必要な事業手続きのオンライン対応一覧表
| 分類 | 成果物 | 提出先 | 頻度 | 内容 | オンライン対応 | 対応の根拠 |
| 給与関連 | 給与明細 | 従業員 | 毎月 | 毎月、社会保険料および所得税、住民税の天引計算をした給与明細を支給する | 可(民間のオンラインサービスを利用) |
― |
| 給与支払報告書 | 都道府県または市町村 | 1月 | 1年間に支払った人件費を市町村に報告する(結果、毎年、6月に住民税が課される) | 可(eLTAX) | *給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには|eLTAX | |
| 源泉所得税関連 | 源泉所得税納付書(納期の特例を利用した場合*) | 税務署 | 7月、1月 | 年2回、納付すべき源泉所得税を計算し、納付書を作成する
*原則、毎月納付書の作成・納付、特例の利用で年2回となる |
可(e-Tax) | *ダイレクト納付による納税手続|e-Tax |
| 源泉徴収票 | 従業員 | 12月 | 従業員の年間所得税を年末調整作業により確定する | 可(e-Tax) | *源泉徴収票等のオンライン送信に係る仕様書一覧|e-Tax | |
| 法定調書 | 税務署 | 1月 | 1年間に支払った人件費や外注費等を税務署に報告する | 可(e-Tax) | *法定調書の作成・提出について|e-Tax | |
| 会計関連 | 会計帳簿 |
― |
毎月 | *社内の会計業務
オンラインサービスで会計帳簿を作成する |
可(民間のオンラインサービスを利用) |
― |
| 予算 |
― |
決算後 | *社内の会計業務
翌年度予算をもとに役員報酬をもっとも節税できる水準に決定する |
可(民間のオンラインサービスを利用) |
― |
|
| 試算表 |
― |
決算月 | *社内の会計業務
必要に応じて決算前に試算表を作成し、節税の提案をする(可能であれば毎月作成し、業績を把握する) |
可(民間のオンラインサービスを利用) |
― |
|
| 決算書 | 税務署 | 申告月 | 貸借対照表(B/S)や、損益計算書(P/L)などの会社法で定めた決算書を提出する | 可(民間のオンラインサービスを利用) |
― |
|
| 税金関連 | 法人税申告書 | 税務署 | 申告月 | 法人税を申告する | 可(e-Tax) | *利用可能手続一覧|e-Tax |
| 消費税申告書 | 税務署 | 申告月 | 消費税を申告する | 可(e-Tax) | *【消費税及び地方消費税の申告等】|国税庁 | |
| 償却資産税申告書 | 都道府県または市町村 | 1月 | 備品や機械装置など減価償却資産を持っている場合に申告する(結果、備品等への固定資産税の課税あり) | 可(eLTAX) | *固定資産税(償却資産)を電子申告するには|eLTAX | |
| 健康保険・厚生年金保険 | 算定基礎届 | 年金事務所 | 7月 | 毎年、社会保険料を見直すための報告をする | 可(e-Gov) | *定時決定(算定基礎届)|日本年金機構 |
| 賞与支払届 | 年金事務所 | 賞与支払月 | 賞与支払時の社会保険料の報告をする | 可(e-Gov) | *従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構 | |
| 被保険者資格取得届 | 年金事務所 | 適宜 | 加入、脱退の手続きをする | 可(e-Gov) | *社会保険関係手続 電子申請|日本年金機構 | |
| 標準報酬月額変更届 | 年金事務所 | 適宜 | 社会保険料の適時の見直し手続きをする | 可(e-Gov) | *e-Gov電子申請利用マニュアルの紹介|厚生労働省 | |
| 雇用保険・労災保険 (従業員がいる場合) |
労働保険料申告書 | 労働基準監督署 | 7月 | 毎年、労働保険料を見直す報告をする | 可(e-Gov) | *労働保険関係手続の電子申請について|厚生労働省 |
| 36協定 | 労働基準監督署 | 毎年1回 | 残業時間について合意し、届出する | 可(e-Gov) | *厚生労働省のP DF資料:労働基準法、最低賃金法等の届出等は、電子申請が便利です | |
| 被保険者資格取得届 | 公共職業安定所 | 適宜 | 雇用保険の加入、脱退の手続きをする | 可(e-Gov) | *申請等をご利用の方へ|ハローワークインターネットサービス |
その他の事業手続きのオンライン対応
これまでにあげたもの以外にもオンライン手続きできるものはあります。
経済産業省「GビズID(gBizID)」という行政サービスにログインできるサービスの利用で、各省庁の電子申請ができます。
e-Govでの利用はもちろん、補助金の申請などにも使えるので、ぜひ活用しましょう。
GビズIDで利用できる行政サービス一覧|gBizID
*一覧はページ半ばにあります
郵送の申請手続きの注意
オンライン手続き(電子申請)はできなくとも、申請書をダウンロードまたはメールで送付してもらい、郵送で申請できる手続きもあります。
郵送の場合、重要書類のため、必ず郵便局に行って、書留などの記録に残る送付方法をとらなければなりません。
間違っても重要書類を送るのに切手を貼って郵便ポストへ投函しないようにしましょう。あくまで、遠方の提出先が、最寄りの郵便局にまで近くなったと考えましょう。
資金調達分野:融資の手続きのオンライン対応
資金調達分野、融資の手続きもオンラインサービスは充実してきています。
例えば、2021年5月より日本政策金融公庫の事業資金の融資も、オンラインで申し込みできるようになっています。
あくまで申し込み部分のオンライン対応で、すべてがリモートで行えるサービスを提供するものではありませんので、ご注意ください。通常行われる融資担当との面談が、電話での聞き取りに置き換わるなど、コロナ禍では対面しなくてよいケースもありましたが、今後も続く対応とは限りません。
創業期を終えて軌道にのって融資を受けたいと考える場合は、すべての過程がオンラインで完結する融資(オンライン融資)を検討するのがよいでしょう。
まとめ
新しい創業のあり方として、非対面型ビジネスモデルで、創業〜事業経営の手続きもオンラインを前提とした持続可能な経営を目指す「リモート創業」をご提案しました。
リモート創業は一見、地に足がついていないように見えるかもしれませんが、名よりも実をとる事業のあり方です。目まぐるしく変わる社会情勢に振り回されないよう、本当に必要なものを見つめた創業〜事業経営に取り組みましょう。
創業を考えている方、コロナ禍で経営に不安がある人は、国が認めた経営問題に関する相談・支援をする認定支援機関の株式会社SoLabo(ソラボ)にぜひご相談ください。経営アドバイスから、融資(ローン)に必要な書類の作成、審査の進行管理や面談対策まで、事業者向けの経営サポートを行っています。